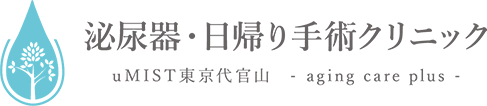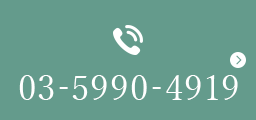前立腺肥大症とは?症状と治療の必要性
前立腺肥大症は、男性の尿道を取り囲む前立腺が異常に増大することで起こる疾患です。前立腺は膀胱のすぐ下に位置し、尿道を取り囲んでいるため、肥大すると尿道が圧迫され、排尿に関するさまざまな症状が現れます。
主な症状としては、頻尿、夜間頻尿、尿勢低下、排尿困難、残尿感、尿意切迫感などが挙げられます。これらの症状は加齢とともに増加し、50歳以上の男性の約半数が何らかの症状を経験すると言われています。
前立腺肥大症は生命を脅かす疾患ではありませんが、症状が進行すると日常生活の質を著しく低下させます。さらに、尿閉(尿が出なくなる)、血尿、膀胱結石、尿路感染症などの合併症を引き起こすリスクもあります。これらの症状や合併症が現れた場合、適切な治療が必要となります。
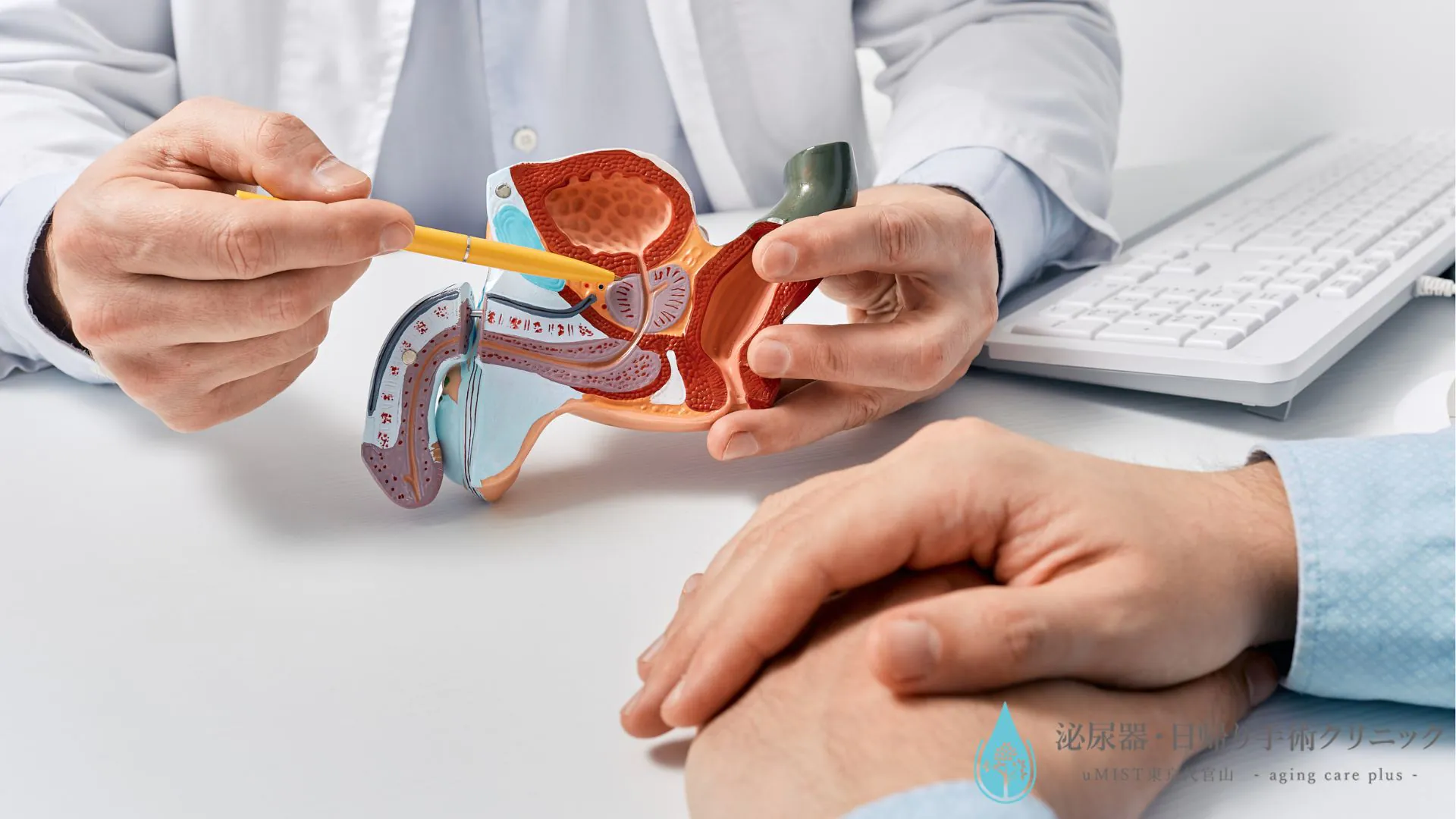
目次
前立腺肥大症の従来治療法とその限界
前立腺肥大症の治療は、症状の程度や前立腺の大きさ、患者さんの全身状態などを考慮して選択されます。従来の治療法は大きく分けて、薬物療法と外科的治療に分類されます。
薬物療法の概要と限界
薬物療法は主にα遮断薬や5α還元酵素阻害薬が用いられます。α遮断薬は前立腺や膀胱頸部の平滑筋を弛緩させ、尿道の圧迫を軽減します。5α還元酵素阻害薬は前立腺の肥大を抑制し、サイズを縮小させる効果があります。
しかし、薬物療法には限界もあります。効果が現れるまでに時間がかかる場合があり、また、長期間の服用が必要となります。副作用として、α遮断薬では立ちくらみや鼻閉、5α還元酵素阻害薬では性機能障害などが報告されています。さらに、薬物療法では根治には至らず、症状が進行するリスクも残ります。
従来の外科的治療法(TURP)
薬物療法で効果が不十分な場合や、尿閉などの合併症がある場合は外科的治療が検討されます。従来の標準的な手術方法は経尿道的前立腺切除術(TURP:Transurethral Resection of the Prostate)です。
TURPは尿道から内視鏡を挿入し、電気メスで肥大した前立腺組織を切除する方法です。効果は高く、多くの患者さんで症状の改善が見られます。しかし、全身麻酔または腰椎麻酔が必要で、入院期間も5〜8日程度と比較的長くなります。
さらに、TURPには出血、尿道狭窄、一時的な尿失禁、射精障害(逆行性射精)などの合併症リスクがあります。特に射精障害は高率(約65%)に発生するため、性機能の温存を望む患者さんにとっては大きな懸念事項となっています。
低侵襲治療(MIST)の登場と進化
前立腺肥大症治療の課題を解決するため、近年さまざまな低侵襲治療(Minimally Invasive Surgical Treatments: MIST)が開発されてきました。これらの治療法は、従来のTURPと比較して体への負担が少なく、合併症リスクも低減されています。
低侵襲治療のメリット
低侵襲治療の主なメリットは以下の通りです:
- ・短い手術時間と入院期間
- ・局所麻酔や鎮静で実施可能な場合が多い
- ・出血などの合併症リスクが低い
- ・性機能障害(特に射精障害)の発生率が低い
- ・早期の日常生活への復帰が可能
- ・抗凝固薬を中止せずに治療可能な場合がある
これらのメリットにより、高齢者や合併症を持つ患者さん、性機能温存を希望する患者さんなど、従来のTURPが適さない、あるいはリスクが高いと考えられる方々にも治療の選択肢が広がっています。
主な低侵襲治療法の比較
現在、日本で実施されている主な低侵襲治療法には、経尿道的前立腺吊り上げ術(UroLift)、経尿道的水蒸気治療(WAVE/Rezūm)、一時的埋め込み型ニチノールデバイス(iTind)、前立腺動脈塞栓術(PAE)などがあります。それぞれの特徴と効果を比較してみましょう。
経尿道的前立腺吊り上げ術(UroLift/PUL)
UroLift(ウロリフト)は、前立腺内に小型のインプラントを埋め込み、肥大した前立腺組織を吊り上げて尿道を広げる治療法です。前立腺組織の切除や焼灼を行わないため、体への負担が少なく、性機能も温存されやすいのが特徴です。
手術時間は約15分と短く、局所麻酔下で実施可能です。日本では2022年4月に保険適用となり、現在多くの医療機関で実施されています。欧米では2013年から導入されており、30万人以上が治療を受け、長期効果が実証されています。
システマティックレビューによると、UroLiftは短期的な追跡調査では、TURPと比較して排尿症状スコアにほとんど差がない可能性があります(MD 1.47、95%CI -4.00~6.93)。また、主要な有害事象も大幅に減少する可能性があります(RR 0.30、95%CI 0.04~2.22)。
経尿道的水蒸気治療(WAVE/Rezūm)
Rezūm(レズム)システムは、高周波を使用して水蒸気の形で熱エネルギーを発生させ、前立腺組織をアブレーション(破壊)する治療法です。水蒸気が前立腺組織に接触すると、熱エネルギーが放出され、アポトーシス(細胞死)と壊死を引き起こします。
この治療法の特徴は、前立腺の境界を超えて熱の影響が見られず、尿道、膀胱頸部、外括約筋に影響を与えないことです。治療は意識下鎮静を使用して実施され、手術時間も短時間で済みます。
システマティックレビューによると、CRFWVTはTURPと比較して排尿症状スコアが若干悪化する可能性がありますが、信頼区間にはほとんど差がない可能性も含まれています(MD 3.60、95%CI -4.25~11.46)。主要な有害事象は減少する可能性があります(RR 0.37、95%CI 0.01~18.62)。
一時的埋め込み型ニチノールデバイス(iTind)
iTind(アイティンド)は、一時的に前立腺尿道内に留置する新しいデバイスです。このデバイスは、前立腺尿道内に留置されると拡張し、膀胱頸部と前立腺尿道の形状を変えます。留置後5日で外来診療で除去されます。
オリンパス社が提供するiTindは、すでに米国および欧州で販売されており、アジア太平洋地域でも利用可能になっています。米国では、米国泌尿器科学会(AUA)が2023年9月にBPHに起因するLUTSの治療オプションとしてiTindを含む治療ガイドラインを発表しました。
システマティックレビューによると、TINDはTURPと比較して排尿症状スコアが悪化する可能性がありますが、信頼区間にはほとんど差がない可能性も含まれています(MD 7.50、95%CI -0.68~15.69)。主要な有害事象は減少する可能性があります(RR 0.52、95%CI 0.01~24.46)。
前立腺動脈塞栓術(PAE)
前立腺動脈塞栓術(PAE)は、前立腺に血液を供給する動脈を塞栓材で閉塞させることで、前立腺の虚血や低酸素症を引き起こし、前立腺の萎縮を促す治療法です。これにより前立腺が柔らかくなり、尿道の圧迫が軽減されます。
PAEは泌尿器科医ではなく、放射線科医(インターベンショナルラジオロジスト)によって実施されることが多く、大腿動脈または橈骨動脈からカテーテルを挿入して行われます。
システマティックレビューによると、PAEはTURPと比較して排尿症状スコアにほとんど差がない可能性があります(MD 1.55、95%CI -1.23~4.33)。主要な有害事象も減少する可能性があります(RR 0.65、95%CI 0.25~1.68)。ただし、再治療率はTURPより高くなる可能性があります(RR 4.39、95%CI 1.25~15.44)。
低侵襲治療の有効性と安全性のエビデンス
2021年に発表されたコクランレビューでは、BPHによるLUTSを持つ男性に対する低侵襲治療(MIT)の有効性を評価するために、3,017名の参加者を含む27件の試験が分析されました。このシステマティックレビューとネットワークメタアナリシスの結果から、低侵襲治療の有効性と安全性に関する重要な知見が得られています。
排尿症状と生活の質への効果
短期追跡調査(3〜12ヶ月)では、前立腺尿道リフト(PUL)と前立腺動脈塞栓術(PAE)は、TURPと比較して排尿症状スコアにほとんど差がない可能性があることが示されました。対流高周波水蒸気療法(CRFWVT)、経尿道マイクロ波温熱療法(TUMT)、一時的埋め込み型ニチノールデバイス(TIND)は、TURPと比較して症状スコアが若干悪化する可能性がありますが、信頼区間にはほとんど差がない可能性も含まれています。
生活の質に関しては、すべての低侵襲治療はTURPと比較してほとんど差がない可能性があることが示されました。これは、低侵襲治療が患者さんの日常生活の質の改善においても、従来の手術と同等の効果を持つ可能性を示唆しています。
合併症と安全性プロファイル
主要な有害事象については、経尿道マイクロ波温熱療法(TUMT)はTURPと比較して大幅に減少する可能性が高いことが示されました(RR 0.20、95%CI 0.09~0.43)。その他の低侵襲治療(PUL、CRFWVT、TIND、PAE)も主要な有害事象を減少させる可能性がありますが、信頼区間には大きな利益と害が含まれています。
軽微な有害事象としては、尿路感染症、血尿、排尿困難、血精液症、疼痛などが報告されています。PAEでは「塞栓後症候群」と呼ばれる、主に疼痛、倦怠感、頻尿を特徴とする症状が報告されています。
性機能への影響
低侵襲治療が勃起機能に及ぼす影響については、エビデンスの確実性が非常に低く、明確な結論は得られていません。しかし、射精機能に関しては、PUL、PAE、TUMTはTURPと比較して射精障害の発生率が低い可能性があることが示唆されています。
特にPULは射精機能の温存において最も効果的である可能性が高いとされています(RR 0.05、95%CI 0.00~1.06)。これは、性機能の温存を重視する患者さんにとって重要な情報となります。
どの治療法が最適か?患者個別の選択基準
前立腺肥大症の低侵襲治療は、それぞれ特徴が異なるため、患者さん一人ひとりの状態や希望に合わせて最適な治療法を選択することが重要です。以下に、治療法選択の際に考慮すべき要素を紹介します。
前立腺の大きさと形状による選択
前立腺の大きさや形状は、治療法の選択に大きく影響します。例えば、UroLiftは前立腺容量が20〜70mLの場合に適していますが、中葉の肥大が顕著な場合は効果が限定的な場合があります。一方、PAEは比較的大きな前立腺(40mL以上)に対しても効果が期待できます。
前立腺の膀胱内突出が顕著な場合は、UroLiftよりもCRFWVTやTURPなどの組織除去を行う治療法が適している可能性があります。治療前の詳細な画像検査により、最適な治療法を判断することが重要です。
合併症と既往歴を考慮した選択
患者さんの合併症や既往歴も治療法選択の重要な要素です。抗凝固薬を服用している患者さんでは、出血リスクの低いUroLiftやiTindが適している場合があります。また、ツリウムレーザー前立腺蒸散術(ThuVAP)も抗凝固薬を中止せずに安全に実施できる可能性があります。
心疾患や呼吸器疾患など、全身麻酔のリスクが高い患者さんでは、局所麻酔で実施可能な低侵襲治療が適しています。また、糖尿病や神経因性膀胱など、排尿機能に影響を与える基礎疾患がある場合は、治療効果や合併症リスクが異なる可能性があるため、専門医との十分な相談が必要です。
患者の希望と生活スタイルに合わせた選択
患者さんの希望や生活スタイルも治療法選択の重要な要素です。性機能の温存を重視する場合は、射精障害のリスクが低いUroLiftやiTindが適している可能性があります。また、早期の社会復帰を希望する場合は、入院期間が短い低侵襲治療が適しています。
治療の持続性や再治療のリスクも考慮すべき要素です。TURPは長期的な効果が実証されていますが、低侵襲治療では再治療が必要となる可能性があります。特にTUMTでは再治療率が高くなる可能性が示されています(RR 9.71、95%CI 2.35~40.13)。
患者さんの価値観と嗜好に関する最近のシステマティックレビューでは、男性はTURPと比較して低侵襲治療で高い成功率、低い寛解率、低い合併症率を期待していることが明らかになっています。また、性機能の温存も重視されていることが分かっています。
低侵襲治療の将来展望と課題
前立腺肥大症の低侵襲治療は急速に進化しており、今後もさらなる発展が期待されています。一方で、長期的な有効性や安全性に関するエビデンスの蓄積など、いくつかの課題も残されています。
長期的有効性と安全性のエビデンス構築
多くの低侵襲治療は比較的新しい治療法であり、長期的な有効性や安全性に関するエビデンスはまだ限られています。特にCRFWVTやiTindなどの新しい治療法については、3か月後に盲検期間が終了し、患者が実治療群に移行した研究が多いため、長期的な効果を評価することが難しい状況です。
米国泌尿器科学会ガイドライン委員会は、外科的治療オプションに関する意思決定は12か月を超える追跡データに基づくべきであるとしています。今後、より長期の追跡調査を行い、さまざまな治療法を比較する質の高い研究が必要とされています。
個別化医療と治療選択の最適化
前立腺肥大症の症状や進行度、前立腺の大きさや形状、患者さんの合併症や希望は多様です。そのため、一人ひとりの患者さんに最適な治療法を選択するための個別化医療の重要性が高まっています。
今後は、患者さんの特性や希望に基づいて最適な治療法を予測するためのアルゴリズムや意思決定支援ツールの開発が期待されます。また、複数の治療法を組み合わせたハイブリッド治療なども検討されるかもしれません。
利用可能な選択肢について話し合う際には、臨床医が患者さんと共同意思決定を行うことが重要です。患者さんの価値観や希望を尊重し、利用可能な治療選択肢のメリットとデメリットを十分に説明した上で、最適な治療法を選択することが求められます。
まとめ:患者中心の治療選択の重要性
前立腺肥大症の低侵襲治療は、従来のTURPと比較して体への負担が少なく、合併症リスクも低減された治療選択肢を提供しています。システマティックレビューとネットワークメタアナリシスの結果から、これらの治療法は短期的な追跡調査ではTURPと比較して排尿症状や生活の質に関して同等かそれよりも悪い結果をもたらす可能性がありますが、主要な有害事象は大幅に減少する可能性があることが示されています。
特に前立腺尿道リフト(PUL)と前立腺動脈塞栓術(PAE)は症状スコアのランキングが向上し、PULは他の介入と比較して再治療回数が少なくなる可能性があります。これらの治療法が勃起機能に及ぼす影響については非常に不確実ですが、射精障害の症例は減少する可能性があります。
最適な治療法の選択は、前立腺の大きさや形状、患者さんの合併症や既往歴、そして何より患者さん自身の希望や価値観に基づいて行われるべきです。排尿症状、再治療率、性機能などの有害事象に対する効果を患者さんが重視していることを考えると、さまざまな治療オプションについて話し合う際には、既存の不確実性を強調し、患者さんの希望を引き出した上で、共同意思決定を行うことが必要です。
前立腺肥大症の低侵襲治療は今後もさらなる発展が期待されています。より長期の追跡調査を行い、さまざまな治療法を比較する質の高い研究を実施することで、これらの介入の相対的な有効性に関するより多くの情報が得られる可能性があります。
前立腺肥大症でお悩みの方は、まずは泌尿器科専門医に相談し、自分に最適な治療法について十分に話し合うことをお勧めします。低侵襲治療は多くの患者さんにとって有望な選択肢となりますが、個々の状況に応じた適切な判断が重要です。

〈著者情報〉
泌尿器日帰り手術クリニック
uMIST東京代官山 -aging care plus-
院長 斎藤 恵介