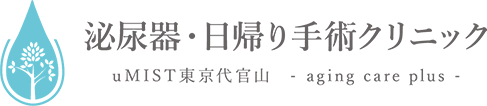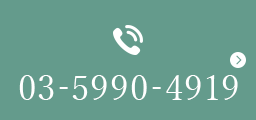前立腺肥大症とは〜患者さんが抱える生活の悩み
前立腺肥大症は、50歳以上の男性に多く見られる疾患です。前立腺は膀胱の下にあり、尿道を取り囲む臓器ですが、加齢とともに肥大し、尿道を圧迫することで様々な排尿トラブルを引き起こします。
患者さんは「夜間に何度もトイレに起きる」「尿の勢いが弱い」「残尿感がある」といった症状に悩まされます。これらは単なる不快感にとどまらず、睡眠の質の低下や社会活動の制限など、生活の質(QOL)を著しく低下させる原因となります。
私の診療では、「外出先でトイレの場所を常に気にしなければならない」「長距離ドライブができなくなった」と訴える患者さんが数多くいらっしゃいます。排尿の問題は、男性の自尊心や自信にも影響を与えることがあるのです。
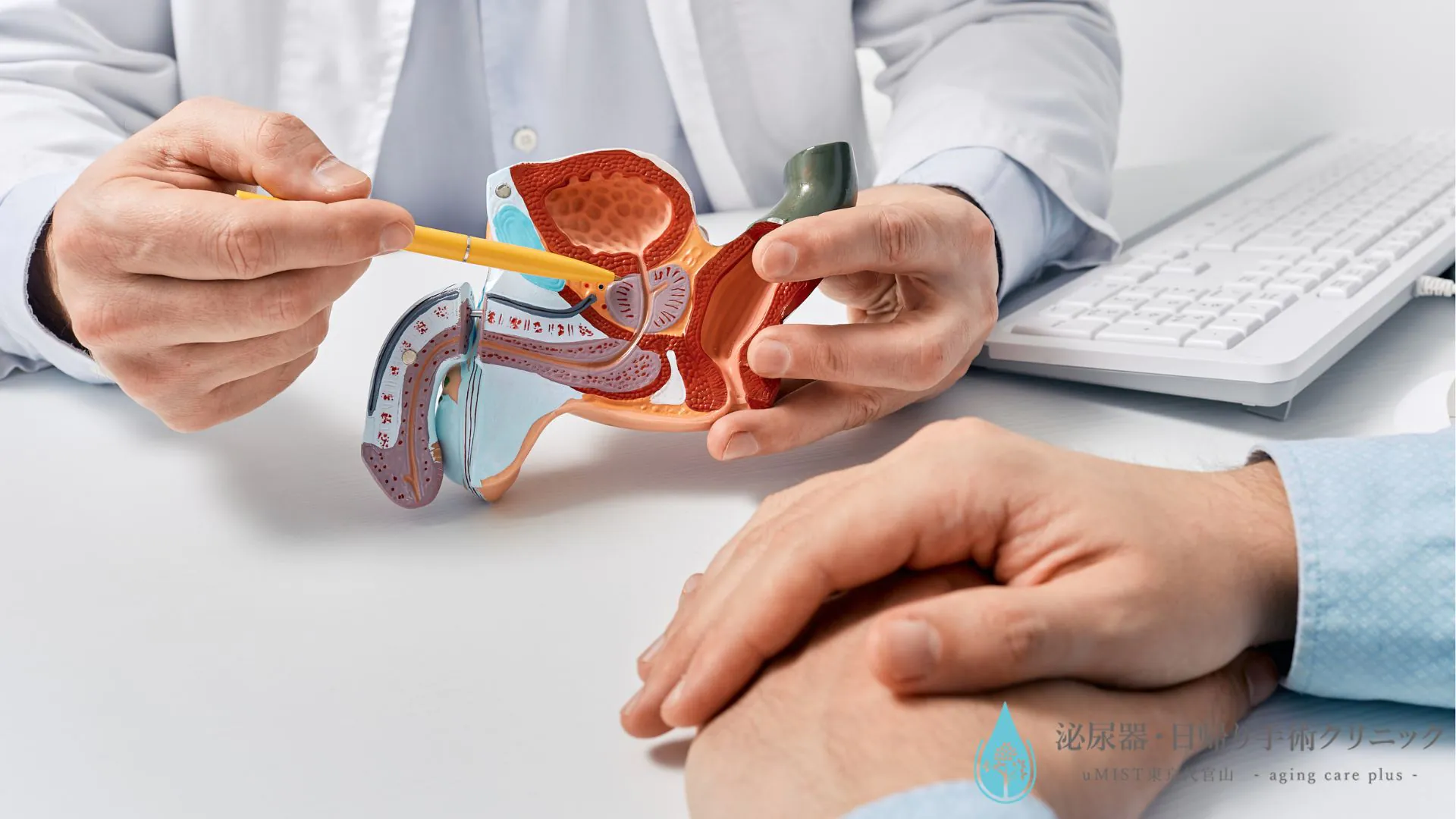
従来の前立腺肥大症治療法とその限界
前立腺肥大症の治療は、症状の程度に応じて段階的に行われます。軽度から中等度の症状には、α遮断薬や5α還元酵素阻害薬などの薬物療法が第一選択となります。しかし、薬物療法には効果の限界があり、副作用の問題も無視できません。
薬物療法で十分な効果が得られない場合や、症状が重度の場合には外科的治療が検討されます。従来の標準的手術は経尿道的前立腺切除術(TURP)でした。TURPは効果が高く確立された治療法ですが、入院期間が比較的長く、出血や性機能障害などの合併症リスクがあります。
特に高齢者や合併症を持つ患者さんでは、全身麻酔や出血のリスクが高まるため、TURPの適応が制限されることがあります。また、抗凝固薬を服用している患者さんでは、薬の休薬が必要となり、脳梗塞や心筋梗塞などのリスクが懸念されます。
私の臨床経験からも、「手術は効果があると聞いているが、入院や合併症が心配で踏み切れない」という患者さんの声をよく耳にします。このような背景から、より低侵襲で安全性の高い治療法の開発が求められてきました。
低侵襲治療(MIST)の登場と進化
近年、前立腺肥大症に対する低侵襲治療(Minimally Invasive Surgical Treatment: MIST)が急速に発展しています。これらの治療法は、従来のTURPと比較して、入院期間の短縮、合併症リスクの低減、回復期間の短縮などのメリットがあります。
最新のシステマティックレビューとネットワークメタアナリシスによると、主な低侵襲治療には以下のものがあります:
- ・対流高周波水蒸気療法(CRFWVT、Rezūm)
- ・前立腺動脈塞栓術(PAE)
- ・前立腺尿道リフト(PUL、UroLift)
- ・一時的埋め込み型ニチノールデバイス(TIND、iTind)
- ・経尿道マイクロ波温熱療法(TUMT)
これらの治療法は、それぞれ異なるメカニズムで前立腺肥大による尿道閉塞を改善します。従来の手術のように前立腺組織を切除するのではなく、組織の再形成や凝固壊死などを利用して症状を改善させるアプローチが特徴です。
私が特に注目しているのは、これらの低侵襲治療が、従来は手術適応とならなかった患者さん、例えば高齢者や合併症を持つ患者さん、抗凝固薬を服用している患者さんにも適用できる可能性がある点です。治療の選択肢が広がることは、患者さんのQOL向上に大きく貢献します。
対流高周波水蒸気療法(Rezūm)の特徴と効果
対流高周波水蒸気療法(CRFWVT)、通称Rezūm(レジューム)システムは、高周波を使用して水蒸気の形で熱エネルギーを発生させ、前立腺組織をアブレーション(焼灼)する治療法です。
Rezūmシステムは、高周波電源ジェネレータと経尿道的デリバリーデバイスから構成されています。治療は局所麻酔下で行われ、膀胱鏡を用いて前立腺の輪郭を確認した後、治療針を前立腺組織に挿入します。水蒸気の各注入は約9秒間続き、前立腺の各葉に複数回注入を行います。
水蒸気が前立腺組織に接触すると、蓄積された熱エネルギーが放出され、細胞のアポトーシス(細胞死)と壊死を引き起こします。重要なのは、前立腺の境界を超えて熱の影響が見られず、尿道、膀胱頸部、外括約筋は影響を受けないという点です。
臨床試験では、Rezūmによる治療後、患者の国際前立腺症状スコア(IPSS)が有意に改善し、その効果は少なくとも3年間持続することが示されています。また、性機能への影響も最小限であり、射精障害のリスクが低いことも大きな利点です。
私の臨床経験では、Rezūmは特に中葉肥大を伴う症例や、性機能温存を希望する比較的若い患者さんに適しています。手術時間も約15分程度と短く、日帰り手術も可能であるため、患者さんの負担が少ないのが特徴です。
前立腺尿道リフト(UroLift)による新しいアプローチ
前立腺尿道リフト(PUL)、商品名UroLiftは、前立腺組織を切除せずに尿道を開存させる画期的な治療法です。2022年4月に日本でも保険適用となり、急速に普及しています。
UroLiftシステムは、デリバリーデバイスとインプラントから構成されています。インプラントは前立腺被膜タブ、尿道エンドピース、そしてそれらを繋ぐ縫合糸からなります。治療は局所麻酔下で行われ、硬性膀胱鏡を用いて前立腺部尿道の2時と10時の位置にインプラントを留置します。
UroLiftの基本的なコンセプトは、インプラントを用いて肥大した前立腺組織を分離・牽引することで、前立腺部尿道の開存性を確保するというものです。従来の手術のように組織を切除・焼灼しないため、出血や性機能障害などの合併症リスクが低いのが特徴です。
臨床試験(L.I.F.T. study)では、UroLiftによる治療後、IPSSスコアの有意な改善が認められ、その効果は5年間持続することが示されています。また、射精機能が温存されることも大きなメリットです。
私の経験では、UroLiftは特に性機能温存を重視する患者さんや、抗凝固薬を服用している患者さんに適しています。手術時間は約15分と短く、術後の尿道カテーテル留置期間も短いため、早期の社会復帰が可能です。
前立腺動脈塞栓術(PAE)の有効性と適応
前立腺動脈塞栓術(PAE)は、血管内治療の一種で、前立腺への血流を遮断することで組織の萎縮を促す治療法です。泌尿器科医と放射線科医の協力のもとで行われる学際的なアプローチです。
PAEは局所麻酔下で行われ、大腿動脈または橈骨動脈から造影剤を注入し、前立腺動脈を同定します。その後、マイクロカテーテルを用いて前立腺動脈に到達し、塞栓物質(マイクロスフィアなど)を注入して血流を遮断します。
PAEの根本的なメカニズムは、前立腺への血流を遮断することで虚血または低酸素症を引き起こし、前立腺の萎縮、壊死、硬化を促すというものです。その結果、前立腺が柔らかくなり、尿道の圧迫が軽減されます。
最新のシステマティックレビューによると、PAEはTURPと比較して短期的な排尿症状スコアにほとんど差がなく、主要な有害事象が大幅に減少する可能性があります。ただし、再治療率はTURPよりも高い傾向があります。
私の臨床経験では、PAEは特に前立腺容積が非常に大きい患者さん(80ml以上)や、手術リスクが高い患者さんに適しています。また、カテーテル挿入が不要な場合が多く、入院期間も短いため、患者さんのQOL向上に貢献します。
一時的埋め込み型ニチノールデバイス(iTind)の新たな可能性
一時的埋め込み型ニチノールデバイス(TIND)、商品名iTindは、前立腺尿道を一時的に拡張することで症状を改善する新しい治療法です。日本では2025年2月にオリンパスが販売地域を拡大し、アジア太平洋地域の主要市場で利用可能になりました。
iTindデバイスは、生体適合性のある超弾性形状記憶合金(ニチノール)で作られた3本の細長い支柱と固定用の弁葉で構成されています。膀胱鏡を用いて前立腺尿道内に留置され、解放されると拡張して膀胱頸部と前立腺尿道の形状を変えます。
デバイスは留置後5日で外来診療で除去されますが、その間に前立腺尿道と膀胱頸部に持続的な圧力を加えることで組織の虚血性壊死を引き起こし、尿道の開存性を確保します。
臨床試験では、iTind留置後のIPSSスコアの有意な改善が認められ、その効果は3年間持続することが示されています。また、性機能への影響も最小限であることが報告されています。
私の見解では、iTindは特に短期間の治療を希望する患者さんや、永久的なインプラント留置を避けたい患者さんに適しています。また、抗凝固薬を服用している患者さんにも適用できる可能性があります。
経尿道マイクロ波温熱療法(TUMT)の位置づけ
経尿道マイクロ波温熱療法(TUMT)は、マイクロ波による熱誘導で前立腺組織を焼灼する治療法です。特殊な経尿道カテーテルを使用し、マイクロ波の電磁放射を介して前立腺に熱を伝えます。
TUMTは外来で行われ、局所麻酔下で治療カテーテルを尿道内に挿入します。カテーテルには温度センサーとマイクロ波ユニットが含まれており、前立腺組織を70℃以上に加熱して熱アブレーションを引き起こします。
最新のシステマティックレビューによると、TUMTはTURPと比較して主要な有害事象を大幅に減少させる可能性が高いものの、排尿症状スコアはTURPよりも悪化する可能性があり、再治療率も高くなる傾向があります。
私の臨床経験では、TUMTは技術的な進歩により他の低侵襲治療に置き換えられつつありますが、特定の患者群、例えば手術リスクが非常に高い患者さんなどには依然として選択肢となり得ます。
低侵襲治療の比較と個別化治療の重要性
前立腺肥大症に対する低侵襲治療は、それぞれ特徴と適応が異なります。治療選択にあたっては、症状の重症度、前立腺の大きさと形状、患者さんの年齢や合併症、性機能温存の希望など、様々な要素を考慮する必要があります。
最新のシステマティックレビューとネットワークメタアナリシスによると、短期的な追跡調査では、PULとPAEはTURPと比較して排尿症状スコアにほとんど差がない可能性がありますが、CRFWVT、TUMT、TINDは症状スコアが悪化する可能性があります。
一方、生活の質に関しては、すべての低侵襲治療がTURPと比較してほとんど差がない可能性があります。主要な有害事象については、すべての低侵襲治療でTURPよりも発生率が低い傾向があります。
再治療率に関しては、TUMTが最も高く、PULが最も低い傾向があります。性機能への影響については、データが限られており不確実性が高いものの、低侵襲治療はTURPよりも射精障害のリスクが低い可能性があります。
私の臨床経験からは、以下のような個別化治療の指針が有用と考えています:
- ・性機能温存を重視する比較的若い患者さん → PUL、Rezūm
- ・前立腺が非常に大きい患者さん → PAE
- ・中葉肥大を伴う患者さん → Rezūm
- ・抗凝固薬を服用している患者さん → PUL、iTind、PAE
- ・短期間の治療を希望する患者さん → iTind
どの治療法を選択するにしても、患者さんの希望と価値観を尊重し、十分な情報提供と共同意思決定が重要です。
まとめ:低侵襲治療がもたらす患者さんのQOL向上
前立腺肥大症に対する低侵襲治療の進化は、多くの患者さんに新たな治療選択肢をもたらしています。これらの治療法は、従来のTURPと比較して、入院期間の短縮、合併症リスクの低減、回復期間の短縮などのメリットがあります。
特に注目すべきは、これらの低侵襲治療が、従来は手術適応とならなかった患者さん、例えば高齢者や合併症を持つ患者さん、抗凝固薬を服用している患者さんにも適用できる可能性がある点です。
現時点でのエビデンスによれば、短期的な症状改善効果はTURPに及ばない可能性がありますが、生活の質の改善はほぼ同等で、合併症リスクは大幅に低減されます。特に性機能温存の観点からは、低侵襲治療は大きなメリットがあります。
私の臨床経験からも、適切に選択された患者さんでは、これらの低侵襲治療により排尿症状の著明な改善と生活の質の向上が得られています。「トイレの心配なく外出できるようになった」「夜間頻尿が減って睡眠の質が向上した」という声をよく耳にします。
前立腺肥大症の治療は、単に排尿症状を改善するだけでなく、患者さんの生活全体の質を向上させることを目指すべきです。低侵襲治療の進化により、より多くの患者さんが、より少ないリスクで、より良い生活を取り戻すことができるようになっています。患者さん一人ひとりの状態と希望に合わせた個別化治療が、これからの前立腺肥大症治療の鍵となるでしょう。

〈著者情報〉
泌尿器日帰り手術クリニック
uMIST東京代官山 -aging care plus-
院長 斎藤 恵介