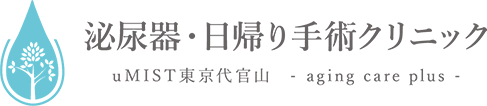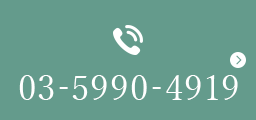フェムテックとは?女性の健康課題を解決する技術の全体像
フェムテック(Femtech)は、「Female(女性)」と「Technology(テクノロジー)」を組み合わせた造語です。女性特有の健康課題や悩みをテクノロジーによって解決する製品やサービスを指します。生理、妊娠、出産、更年期など、女性のライフステージに応じた様々な課題に対して、テクノロジーを活用したソリューションを提供しています。
2025年現在、フェムテックは単なるトレンドを超え、女性のウェルビーイングと社会進出を支える重要な産業へと成長しました。株式会社矢野経済研究所の調査によれば、2023年のフェムケア&フェムテックの市場規模は約750億円に達し、年々拡大傾向にあります。
フェムテックとフェムケアの違いを理解することも重要です。フェムケアは「Female(女性)」と「Care(ケア)」を組み合わせた言葉で、オーガニックコットンの生理用品やデリケートゾーン専用洗浄剤など、女性の健康やウェルビーイングを向上させるための商品・サービスを指します。一方、フェムテックはIoTやAIなどのテクノロジーを活用して女性の健康課題を解決するアプローチです。
なぜ今、フェムテックが注目されているのでしょうか?

目次
フェムテックが注目される3つの背景と社会的意義
フェムテックが近年急速に注目を集めている背景には、社会情勢の変化や女性の健康に対する認識の高まりがあります。具体的には以下の3つの要因が挙げられます。
女性の社会進出の拡大
2016年に女性活躍推進法が施行されるなど、働く女性を後押しする動きが強まっています。それに伴い、これまで見過ごされがちだった女性特有の健康課題が注目されるようになりました。
経済産業省が2024年に発表した調査によれば、月経・PMSや更年期症状による労働生産性の損失は年間約1兆5000億円に上ると試算されています。具体的には、これらの症状があり何も対策を行っていない「無行動層」の欠勤による損失が約4277億円、業務効率低下による損失が約1兆940億円にのぼるとされています。
テクノロジーの進化
IoT、AI、ビッグデータなどのテクノロジーの発展により、女性の健康管理や医療アクセスが格段に向上しました。スマートフォンアプリで生理周期を管理したり、オンライン診療で専門医に相談したりすることが可能になっています。
社会的認識の変化
これまでタブー視されがちだった女性の健康課題について、オープンに議論する文化が徐々に形成されつつあります。「生理の貧困」などの社会課題がメディアで取り上げられ、2021年からは政府の「骨太の方針」にも「フェムテック」の文言が盛り込まれるようになりました。
このような背景から、フェムテックは単なるビジネストレンドを超えて、社会的意義を持つ重要な分野として認識されるようになっています。
2025年フェムテック市場の現状と動向
2025年10月現在、フェムテック市場は急速に拡大し続けています。国内外で様々な革新的サービスが登場し、女性の健康管理や医療アクセスに大きな変革をもたらしています。
海外市場では、米国を中心に大きな成長が見られます。特に注目すべきは、Carrot Fertility、Progyny、Maven Clinicといった企業です。これらの企業は当初、不妊治療や妊活支援から事業を開始し、現在では更年期ケアなど女性のライフステージ全体をサポートするサービスへと水平統合を進めています。
Carrot Fertility
2023年から更年期症状管理のホルモン補充療法(HRT)のサポートや、更年期ケアを専門とする医師とのオンライン・対面診療を提供しています。更年期による生産性低下や早期退職のリスクに対応し、従業員の長期的な定着率向上を目指す包括的なケアを実施しています。
公式サイト:https://www.get-carrot.com/
Flo Health
また、月経管理アプリを提供するFlo Healthは、2024年7月に評価額が10億ドルを超え、ヨーロッパのフェムテック企業として初のユニコーン企業となりました。記録された情報をパートナーとシェアする機能や、医療専門家と連携した正確な知識提供など、ユーザー中心の機能が支持されています。
公式サイト:https://flo.health/ja
日本国内におけるフェムテックの動向
日本国内でも、政府主導の取り組みが活発化しています。「女性版骨太の方針2024」ではフェムテックの推進と更なる利活用が掲げられ、経済産業省による「フェムテック等サポートサービス実証事業費補助金」も継続的に実施されています。この補助金は、フェムテック企業と導入企業、自治体、医療機関等が連携して行う実証事業に対して費用の一部を補助するものです。
東京都も独自の施策を展開しており、事業者向けには「女性活躍のためのフェムテック開発支援・普及促進事業」、企業向けには「フェムテックを導入して職場環境の整備等に取り組む企業向けの奨励金制度」、個人向けには「卵子凍結に係る費用助成」などを実施しています。
医療現場におけるフェムテックの活用事例
医療現場でのフェムテック活用は、患者と医療者双方に大きなメリットをもたらしています。特に注目すべきは、米国で開発された「フェムテックのためのフレームワーク」に基づく革新的なデジタルリプロダクティブヘルスツールです。
このフレームワークは、社会的・経済的に疎外された集団や慢性疾患を持つ人々のためのデジタルリプロダクティブヘルスツールを開発するための3つの重要な指針を提案しています:
- 技術の設計・開発・展開にコミュニティの利害関係者を含めること
- 個人中心の枠組みに根ざすこと
- 健康の公平性を促進する戦略として健康格差に対処すること
これらの原則に基づいて開発された具体的な事例として、以下の4つのツールが挙げられます。
1. MyPath - 退役軍人向け生殖意思決定支援ツール
MyPathは、退役軍人向けの生殖に関する意思決定支援ウェブツールです。プライマリケア受診前に患者が自身の生殖目標を明確にし、医療提供者と共有できるよう支援します。患者の知識を深め、生殖に関するニーズについてコミュニケーションをとる際の自己効力感を高める効果があります。
2. MHP MyHealthyPregnancy - 妊婦向け早産リスク管理アプリ
MHP MyHealthyPregnancyは、妊婦向けのスマートフォンアプリと医療提供者ポータルで構成されるプラットフォームです。アプリを通じて妊婦からリアルタイムでデータを収集し、統計的機械学習アルゴリズムを適用して早産の前兆となる修正可能なリスクを特定します。リスク要因が特定されると医療提供者に通知され、患者には適切なリスク最小化戦略とリソースが提供されます。
このツールの特筆すべき点は、親密なパートナーによる暴力(IPV)やうつ病など、通常の診察では発見されにくいリスク要因も検出できることです。実際の運用では、IPVの身体的リスクを報告した患者の100%が、対面スクリーニングでは報告していなかったという結果が出ています。
公式サイト:https://www.naimahealth.com/myhealthypregnancy
3. MyDecision - 低所得層女性向け不妊手術意思決定支援ツール
MyDecisionは、低所得の英語およびスペイン語圏の女性向けの不妊手術に関する意思決定支援ウェブツールです。偏りのない適切な情報提供と、十分な情報に基づいた価値観に基づく自主的な意思決定プロセスをサポートします。
米国では不妊手術が低所得者や人種的・民族的マイノリティグループによって不釣り合いに多く使用されている背景があり、このツールは低所得女性の身体的・生殖的自立をより良く支援することを目指しています。
4. MyVoice:RheumとMyVoice:CF - 慢性疾患女性向け家族計画支援ツール
これらのツールは、リウマチ性筋骨格系疾患(RMD)および嚢胞性線維症(CF)の女性向けの家族計画ケア支援ツールです。疾患特有の生殖健康上の懸念に対応し、患者が自分の状況に照らして子育て、妊娠、避妊の利点とリスクを理解し、生殖に関する目標を明確にして医療チームに伝えることを支援します。
日本の医療現場でのフェムテック活用の実際
日本の医療現場では、フェムテックの活用がまだ発展途上ですが、着実に広がりを見せています。特に注目すべき活用事例として、大和リース株式会社の取り組みが挙げられます。
同社は「従業員の幸せ」と「会社の幸せ」をともに高めるため、ウェルビーイングや健康につながる福利厚生を積極的に展開しています。産業看護師が常駐する「健康管理室」の設置やフェムテックの活用に加え、2024年5月からは尿がん検査「マイシグナル」を導入し、従業員の健康意識向上とがん早期発見の仕組みづくりに取り組んでいます。
特筆すべきは、若年層の受検率向上のための工夫です。同社では、39歳以下は1万円、40歳以上は2万円で検査を受けられるよう、年齢層別の自己負担額を設定し、差額を会社が負担しています。この結果、30代の受検率は全体平均より高くなったとのことです。
また、医療機関でのフェムテック活用も進んでいます。産婦人科オンラインを提供するKids Publicでは、妊娠・出産に関する相談をオンラインで受け付け、専門医によるアドバイスを提供しています。地方在住者や多忙な女性にとって、医療アクセスの向上に大きく貢献しています。
公式サイト:https://kids-public.co.jp/
フェムテック導入における課題と解決策
フェムテックの普及には多くの可能性がある一方で、いくつかの課題も存在します。ここでは主な課題と、その解決策について考えてみましょう。
1. 企業内での連携不足
フェムテックを職場に導入する際の最大の課題の一つは、人事部門、健保組合、産業医などの関係者間の連携不足です。それぞれが独自の視点や優先事項を持っているため、統一的なアプローチが難しい場合があります。
この課題を解決するためには、フェムテック導入の目的と期待される効果を明確にし、関係者全員で共有することが重要です。また、定期的な情報共有の場を設け、進捗状況や課題について話し合うことも効果的です。
2. 女性の健康課題に対する理解不足
職場において、管理職を含む男性社員が女性特有の健康課題について十分に理解していないケースが多く見られます。これが、フェムテック導入の障壁となることがあります。
解決策としては、全社員を対象とした女性の健康に関する教育プログラムの実施が挙げられます。日本フェムテック協会が提供する「フェムテラシー」認定資格などを活用し、組織全体の理解度を高めることが効果的です。
3. プライバシーとデータセキュリティの懸念
フェムテックサービスは個人の健康データを扱うため、プライバシーとデータセキュリティに関する懸念が大きな課題となります。特に日本では個人情報保護に対する意識が高く、データ提供に抵抗感を持つユーザーも少なくありません。
この課題に対しては、データの匿名化や暗号化などの技術的対策に加え、データの利用目的や保護方針を明確に説明することが重要です。また、ユーザーが自分のデータをコントロールできる仕組みを提供することで、信頼性を高めることができます。
4. 持続可能なビジネスモデルの構築
フェムテックサービスの多くは、初期段階では補助金や投資に依存しており、長期的な収益モデルの確立が課題となっています。特に日本市場では、ユーザーの支払い意欲が限定的であることも障壁となっています。
解決策としては、B2B2Cモデルの採用が考えられます。企業や健康保険組合を通じてサービスを提供することで、安定した収益基盤を確保することができます。また、基本機能は無料で提供し、高度な機能やパーソナライズされたサービスに課金するフリーミアムモデルも効果的です。
参考文献:フェムテックのためのフレームワーク:米国におけるデジタルリプロダクティブヘルスツール開発の指針
フェムテックが切り拓く未来の医療と社会
フェムテックの発展は、医療のあり方だけでなく、社会全体に大きな変革をもたらす可能性を秘めています。ここでは、フェムテックが切り拓く未来の展望について考察します。
医療面
パーソナライズドメディシンの進化が期待されます。フェムテックデバイスやアプリから収集されるビッグデータとAIの活用により、個々の女性の健康状態や体質に合わせた、より精密な医療サービスの提供が可能になるでしょう。例えば、生理周期や基礎体温のデータから、特定の疾患のリスクを早期に検知し、予防的な介入を行うことができるようになります。
社会的な観点
女性の健康課題に対する認識の向上と、それに伴う働き方や生活環境の変化が期待されます。フェムテックの普及により、これまでタブー視されがちだった女性特有の健康課題について、オープンに議論する文化が形成されるでしょう。これにより、職場環境や公共施設のデザインにも女性の健康に配慮した変化が生まれる可能性があります。
健康格差の是正
医療アクセスが限られた地域や、社会経済的に不利な立場にある女性たちにとって、フェムテックは重要な健康管理ツールとなり得ます。オンライン診療や健康モニタリングアプリの普及により、地理的・経済的な障壁を超えた医療サービスの提供が可能になるでしょう。
しかし、これらの可能性を実現するためには、技術の発展だけでなく、社会制度や意識の変革も必要です。医療保険制度におけるフェムテックサービスの位置づけの明確化や、デジタルリテラシーの向上支援など、多角的なアプローチが求められます。
私たち医療者には、フェムテックの可能性を最大限に活かしながら、その限界も認識し、患者さん一人ひとりに寄り添った医療を提供する責任があります。テクノロジーは便利なツールですが、最終的に重要なのは、それを使う人間の温かさと専門性です。
フェムテックは、女性の健康と幸福を支える強力なツールとなる可能性を秘めています。その発展に注目しながら、医療現場での適切な活用方法を模索していくことが、これからの医療者に求められる重要な課題と言えるでしょう。

〈著者情報〉
泌尿器日帰り手術クリニック
uMIST東京代官山 -aging care plus-
院長 斎藤 恵介