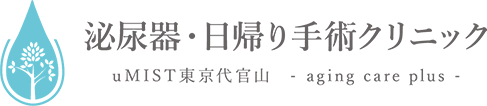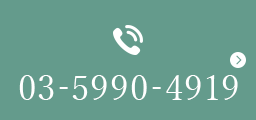閉経はいつから?GSM(閉経関連泌尿生殖器症候群)に注意すべき7つのこと
閉経を迎える時期は女性によって様々ですが、その前後に起こる体の変化に悩む方は少なくありません。特に「GSM(閉経関連泌尿生殖器症候群)」という症状をご存知でしょうか?
閉経に伴うホルモン変化によって引き起こされるこの症状は、多くの女性のQOL(生活の質)を大きく低下させる可能性があります。しかし、適切な知識と対策があれば、その影響を最小限に抑えることができるのです。
この記事では、泌尿器科医の立場から、閉経の時期とGSMの兆候、そして効果的な対策について詳しくご説明します。

目次
閉経とは?平均的な年齢と前兆について
閉経とは、卵巣機能が低下し、女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が減少することで月経が永久に停止する現象です。日本人女性の平均閉経年齢は50歳前後とされていますが、個人差が大きいのが特徴です。
閉経の定義は「最後の月経から1年以上経過した状態」を指します。つまり、実際に閉経したと確定できるのは、生理が完全に止まってから1年後ということになります。
閉経の前兆としては、以下のような変化が現れることが多いです。
- 生理周期の乱れ(4割近くの女性が経験)
- 生理期間の変化(長くなったり短くなったりする)
- 経血量の変化(増加または減少)
- ホットフラッシュ(のぼせや発汗)
- 睡眠障害
ただし、約6人に1人は特に前兆なく突然閉経を迎えるケースもあります。個人差が大きいため、40代から閉経の可能性を視野に入れておくとよいでしょう。
合わせて読みたい:GSMと膀胱炎の関連性〜更年期女性の尿路症状改善法
GSM(閉経関連泌尿生殖器症候群)とは何か?
GSM(Genitourinary Syndrome of Menopause)は、閉経前後の女性に発生する慢性進行性の低エストロゲン状態を指します。従来は「萎縮性膣炎」や「外陰膣萎縮症」と呼ばれていましたが、近年はより包括的な「GSM」という概念で捉えられるようになりました。
この症候群は、外陰膣萎縮、萎縮性膣炎、膀胱・尿道機能不全などを含む症状群です。閉経後女性の10~50%、閉経前女性の15%に発症すると推定されていますが、実際の有病率はより高い可能性があります。
GSMは生命を脅かす疾患ではありませんが、適切な診断と治療がなければ、患者さんの生活の質に重大な影響を及ぼします。
GSMは主に以下の3つの症状カテゴリーに分類されます:
- 性器症状:腟からの不正出血、腟・外陰部の乾燥感、痛み、かゆみ、灼熱感、におい、ゆるみなど
- 性交症状:性交痛、潤いの減少、性感の減弱、性交後出血など
- 尿路症状:排尿障害、頻尿・頻尿感、尿失禁、膀胱炎を繰り返しやすいなど
GSM(閉経関連泌尿生殖器症候群)に注意すべき7つの兆候
GSMの症状は進行性であり、時間とともに悪化する傾向があります。早期発見・早期治療が重要ですので、以下の兆候に注意しましょう。
1. デリケートゾーンの乾燥感
エストロゲンの減少により、膣の粘膜が薄くなり水分保持能力が低下します。膣の乾燥は最も一般的なGSMの症状で、不快感や痛みの原因となります。
私の臨床経験では、多くの患者さんが「何となく違和感がある」程度の軽微な症状から始まり、徐々に強い乾燥感へと進行していくケースが多いです。
2. 外陰部のかゆみや灼熱感
膣や外陰部の粘膜が薄くなることで、かゆみや灼熱感が生じることがあります。特に夜間や入浴後に症状が強くなるケースが多いようです。
これらの症状は単なる加齢現象と思われがちですが、実はGSMの重要な兆候です。我慢せずに専門医に相談することをお勧めします。
3. 性交痛
膣の乾燥や弾力性の低下により、性交時に痛みを感じるようになります。アメリカでの調査によると、閉経女性の約59%が「セックスが魅力的でなくなった」と感じており、その主な原因の一つがこの性交痛です。
性交痛は徐々に悪化し、パートナーとの関係性にも影響を与える可能性があります。早期の対応が重要です。
4. 尿もれ・頻尿
GSMによる症状で最も多いのが「尿もれ・頻尿」で、6割以上の女性が経験しています。エストロゲンの減少は尿道周囲の組織にも影響し、尿失禁や頻尿の原因となります。
特に咳やくしゃみをした時の尿もれ(腹圧性尿失禁)や、トイレに間に合わない切迫性尿失禁が増加します。これらは単なる加齢現象ではなく、適切な治療で改善可能な症状です。
5. 再発性尿路感染症
膣内環境の変化により、病原菌に対する感受性が高まります。膣内のpHが上昇(5.0~7.5)し、保護的な乳酸菌が減少することで、尿路感染症にかかりやすくなります。
閉経後に膀胱炎を繰り返す場合は、GSMが原因である可能性を考慮する必要があります。
6. おりものの変化
エストロゲンの減少により、おりものの量や性状が変化します。一般的には分泌量が減少しますが、炎症を伴う場合は逆に増加することもあります。
「水分多めのおりものが増えてきた」「お風呂から出るとき、腟からお湯がポタポタと出る」といった症状を訴える患者さんも少なくありません。
7. デリケートゾーンのにおいの変化
膣内の細菌叢(フローラ)の変化により、においが気になるようになることがあります。これは乳酸菌の減少と病原菌の増加によるものです。
「生理のときみたいに蒸れたようなニオイがする」「尿臭がキツくなった」といった変化を感じたら、GSMの可能性を考えましょう。
GSM(閉経関連泌尿生殖器症候群)の原因と病態生理
GSMの主な原因は、エストロゲンの減少です。エストロゲンは女性の泌尿生殖器系の健康維持に重要な役割を果たしています。
低エストロゲン状態は、自然閉経だけでなく、以下のような状況でも起こります:
- 外科的誘発閉経(卵巣摘出手術など)
- 放射線療法や化学療法
- 授乳期
- 特定の薬剤使用(抗エストロゲン薬など)
閉経前の正常な膣組織におけるエストロゲン濃度は30~40 pg/mlですが、閉経後は20 pg/ml未満に低下します。この低下により、以下のような変化が起こります:
組織学的変化
エストロゲンの減少により、膣粘膜の表層扁平上皮細胞が減少し、傍基底細胞が増加します。また、コラーゲン・エラスチン線維の喪失や粘膜固有層の血管減少が起こり、組織の弾力性が低下します。
これらの変化により、膣壁が薄く、乾燥し、弾力性を失い、炎症を起こしやすくなるのです。
膣内環境の変化
正常な膣内環境は乳酸菌が優位で、pHは3.5~5.0の弱酸性です。しかし、エストロゲンの減少により乳酸菌が減少し、pHが5.0~7.5に上昇します。
この環境変化により、ガードネレラ、プレボルテラ、アトポビウムなどの病原菌が増加しやすくなり、感染症のリスクが高まります。
GSMのリスク因子としては、経膣分娩の欠如、性交頻度の低下、運動不足、自己免疫疾患、喫煙、アルコール乱用なども挙げられます。
GSM(閉経関連泌尿生殖器症候群)の診断方法
GSMの診断は、症状の評価と身体所見、そして必要に応じて検査を組み合わせて行います。
症状の評価
まずは詳細な問診を行い、症状の種類、程度、持続期間、日常生活への影響などを評価します。1か月以上続く症状が複数ある場合は、GSMの可能性を考慮します。
特に5つ以上の症状がある場合は、GSMの疑いが強いと言えるでしょう。
身体所見
身体診察では、以下のような所見が見られることがあります:
- 膣の乾燥
- 膣の短縮と狭窄
- 組織の脆弱性
- 陰唇癒着
- 陰核包皮の退縮
- 膣皺の消失
- 紅斑または点状出血
- 白帯下
加齢に伴う変化として、陰毛の分布や色素の減少、恥丘や陰唇の容積減少なども見られることがあります。
検査
診断の補助として、以下のような検査が行われることがあります:
- 膣pHの測定:pHが5.0を超える場合は低エストロゲン状態と一致します。
- 膣成熟指数(VMI)の評価:膣組織の表層細胞、中間細胞、傍基底細胞の比率を評価します。低エストロゲン状態はVMI 0~49で表されます。
- 膣病原体スワブ:感染症の有無を確認します。
これらの評価により、GSMの診断と重症度の判定が可能になります。症状が複数あり、生活の質に影響している場合は、早めに専門医を受診することをお勧めします。
GSM(閉経関連泌尿生殖器症候群)の効果的な治療法と対策
GSMの治療は症状の程度や個人の状況に応じて選択されます。以下に主な治療法をご紹介します。
1. 局所エストロゲン療法
GSMの第一選択治療は局所エストロゲン療法です。膣内に直接エストロゲンを補充することで、組織の回復を促します。
- エストラジオールクリーム・錠剤
- エストラジオール膣リング
- 結合型エストロゲンクリーム
局所療法は全身への影響が少なく、正しく使用すれば安全性が高いのが特徴です。症状の改善とともに、徐々に使用頻度を減らしていくことが可能です。
2. 選択的エストロゲン受容体モジュレーター
エストロゲン療法が禁忌の場合(エストロゲン受容体陽性乳がん歴、血栓塞栓症、肝疾患など)、オスペミフェンなどの選択的エストロゲン受容体モジュレーターが代替療法として使用できます。
これらは特に性交痛の改善に効果を示します。
3. 非ホルモン療法
ホルモン療法が適さない、または希望しない方には、以下のような非ホルモン療法があります:
- 膣保湿剤・潤滑剤:症状の一時的緩和に効果的です。
- フラクショナルマイクロアブレーション二酸化炭素レーザー療法:コラーゲン繊維と血管のリモデリングを促進します。
- 経皮的温度制御高周波療法:組織の再生を促します。
これらの治療は、膣の乾燥、外陰膣の緩み、性交痛などを6~12ヶ月間改善する効果があります。
4. 生活習慣の改善
以下のような生活習慣の改善もGSMの症状緩和に役立ちます:
- 刺激物(香料入り石鹸など)の回避
- 定期的な性的活動(血流改善に効果的)
- 骨盤底筋トレーニング(尿失禁改善に効果的)
- 禁煙(血管収縮を防ぎ、分泌物減少を防止)
- 適度な運動(全身の血流改善)
特に骨盤底筋トレーニングは、尿もれの改善に効果的です。専門家の指導のもとで正しく行うことをお勧めします。
5. 定期的な専門医の受診
GSMは進行性の症状であるため、定期的な専門医の受診が重要です。症状の変化や治療効果を評価し、必要に応じて治療法を調整することで、QOLの維持・向上が期待できます。
GSMは生命を脅かす疾患ではありませんが、適切な診断と治療がなければ、生活の質に重大な影響を及ぼす可能性があります。症状に気づいたら、我慢せずに専門医に相談することをお勧めします。
GSM(閉経関連泌尿生殖器症候群)に対するインティマレーザー治療
当院では、更年期以降に増えるGSM(閉経関連泌尿生殖器症候群)に対し、
インティマレーザーによる非ホルモン治療を行っています。
インティマレーザーの特徴と効果
インティマレーザーは、膣内や外陰部にレーザーエネルギーを照射して粘膜を温め、コラーゲン再生や血流改善を促す治療法です。GSMによる膣や外陰部の不快症状を根本から改善し、ホルモン療法に頼らない、身体への負担が少ない自然な回復を目指す点が大きな特徴です。
レーザーの熱刺激により、膣壁がふっくらとハリを取り戻し、乾燥や痛み、尿漏れなどの症状改善が期待できます。
主な治療の特徴としては切らない・痛みが少ない・日帰りで可能です。
このような方におすすめです
膣の乾燥や性交痛が気になる
尿漏れ・頻尿など排尿トラブルを改善したい
ホルモン治療ができない、または避けたい
出産や加齢による膣のゆるみを改善したい
安全性と施術について
治療は麻酔クリームなどを使用し、痛みを感じることはなく施術時間も約20〜30分で、治療後すぐに日常生活へ戻ることが可能です。数回の施術で持続的な改善効果が得られます。
参考文献:閉経前後の女性の視点が更年期泌尿生殖器症候群(GSM)の尿路要素に与える影響に関する質的研究
まとめ:閉経とGSM(閉経関連泌尿生殖器症候群)への向き合い方
閉経は女性の人生における自然な変化ですが、それに伴うGSM(閉経関連泌尿生殖器症候群)は適切に対処することが重要です。
GSMの主な症状として、膣の乾燥、かゆみ、性交痛、尿もれ、頻尿、再発性尿路感染症などがあります。これらは女性のQOLを大きく低下させる可能性がありますが、適切な治療で改善することが可能です。
治療法としては、局所エストロゲン療法、選択的エストロゲン受容体モジュレーター、非ホルモン療法(保湿剤、レーザー療法など)、生活習慣の改善などがあります。個々の状況に合わせた適切な治療を選択することが大切です。
閉経前後の体の変化に不安を感じたら、一人で悩まず専門医に相談しましょう。正しい知識と適切な治療により、閉経後も快適な生活を送ることができます。
あなたの体の変化に敏感になり、早期に対応することが、健やかな生活を維持するための鍵となります。

〈著者情報〉
泌尿器日帰り手術クリニック
uMIST東京代官山 -aging care plus-
院長 斎藤 恵介