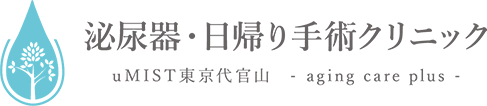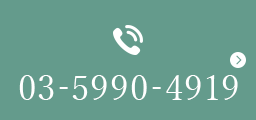夜間頻尿とは?多くの方を悩ませる症状の実態
夜間頻尿は、夜寝ついてから朝起きるまでの間に、1回以上トイレに行くために起きなければならない症状です。特に2回以上の夜間排尿がある場合、生活の質に大きな影響を及ぼします。
私が日々の診療で出会う患者さんの多くは、この症状に長年悩まされています。夜間頻尿は下部尿路症状の中で最も頻度が高く、加齢とともに男女ともに増加することが知られています。
実は、65歳以上の高齢者の約50%がこの症状を訴えており、決して珍しいものではありません。しかし、多くの方が「年だから仕方ない」と諦めてしまっているのが現状です。
夜間頻尿は単なる不便さだけでなく、睡眠の質の低下、日中の疲労感、そして転倒や骨折のリスク増加にもつながります。実際、2回以上の夜間頻尿がある方は、転倒や骨折のリスクが高くなり、死亡率も増加するという報告もあるのです。

目次
夜間頻尿の3つの主要メカニズム
夜間頻尿のメカニズムは大きく分けて3つあります。それぞれのメカニズムを理解することが、適切な治療法を選択する上で非常に重要です。
夜間多尿
夜間の尿量が過剰に増加する状態を指します。65歳を超える方では、24時間の尿量のうち、夜間の尿量が33%を超える場合を夜間多尿と判断します。
この夜間多尿の背景には、実は非常に興味深い生理学的メカニズムが存在します。健康な若年者では、アルギニンバソプレシン(AVP)という抗利尿ホルモンが夜間に多く分泌されることで、夜間の尿量を減少させています。
しかし加齢に伴い、このAVPの夜間分泌が減少することで、夜間の尿量が増加してしまうのです。最新の研究では、このホルモンが腎臓だけでなく、膀胱の機能にも直接影響を与えていることが明らかになっています。
膀胱蓄尿障害
これは膀胱自体の問題で、膀胱容量が低下したり、尿を十分に溜められなくなったりする状態です。
過活動膀胱や前立腺肥大症がこの典型例で、膀胱が過敏になって少量の尿でも強い尿意を感じたり、前立腺の肥大により膀胱出口が閉塞されることで様々な排尿トラブルが生じたりします。
夜間に2回以上トイレに行く患者さんの約31%が過活動膀胱であるという調査結果もあります。私の臨床経験でも、特に高齢の男性患者さんでは、前立腺肥大症と夜間頻尿が合併しているケースが非常に多いです。
睡眠と夜間頻尿の密接な関係
睡眠障害
夜間頻尿と不眠は互いに関係し、悪循環を引き起こすことが知られています。
最近の研究では、適切な時刻に規則正しく就寝する生活を送ることで、高齢者の夜間頻尿が改善する可能性が示されています。これは非常に興味深い発見です。
福井大学医学部付属病院泌尿器科の研究チームは、睡眠・覚醒活動を測定するウェアラブルデバイスを用いて、患者ごとに適切な就寝時刻を決定し、その時刻に就寝する生活を続けることによる夜間頻尿の変化を検証しました。
その結果、介入期間中の夜間排尿回数は、非介入期間と比較して有意に減少したのです(-0.90回 vs -0.01回)。さらに、就寝から第一覚醒までの時間も大幅に延長しました。
高齢者は最適な就寝時刻より早く就寝している傾向があり、これが夜間頻尿を悪化させている可能性があるのです。適切な時刻に規則正しく就寝することで、睡眠の質が向上し、夜間尿量が減少するという結果は、非常に示唆に富んでいます。
あなたは自分の就寝時間を見直したことがありますか?
また、高齢になると深い睡眠が減り、中途覚醒が多くなります。この中途覚醒は膀胱容量の低下を招き、夜間頻尿につながるという悪循環を生み出しているのです。
膀胱からの水分再吸収という新発見
夜間頻尿のメカニズムに関する最新の研究成果として特筆すべきは、膀胱からの水分再吸収という現象です。これまで膀胱は単に尿を貯める器官と考えられてきましたが、実は水分を再吸収する機能も持っていることが明らかになってきました。
哺乳類尿路上皮のアンブレラ細胞と中間細胞の基底外側表面上に存在するアクアポリン2(AQP2)チャネルは、溶質を含まない水の再吸収の分子経路を提供しています。
この発見は、夜間頻尿の新たな治療アプローチの可能性を示唆しています。健康な成人の睡眠中に定期的に超音波測定を行った研究では、膀胱容量が客観的に減少していることが確認されており、これは膀胱膨張によって増強される尿の再吸収を介して夜間の膀胱容量を調節し、満腹感を遅らせるメカニズムが存在することを示唆しています。
加齢に伴い、この膀胱からの尿の恒常的な再吸収機能が低下することが、夜間多尿症や夜間頻尿の一因となる可能性があるのです。
私の臨床経験からも、高齢の患者さんほど夜間頻尿の症状が強く現れる傾向があり、これはこの再吸収機能の低下と関連している可能性があります。
デスモプレシン治療の可能性と注意点
夜間頻尿の治療法として、デスモプレシン(dAVP)という薬剤が使用されることがあります。これは抗利尿ホルモンであるAVPの合成類似体で、夜間多尿、夜尿症を伴う夜間頻尿の治療に用いられます。
デスモプレシンは腎臓の集合管に作用して水の再吸収を促進し、尿量を減少させる効果があります。最近の研究では、デスモプレシンが膀胱にも直接作用して水分再吸収を増加させる可能性も示唆されています。
しかし、特に腎機能が低下している可能性のある高齢者においては、水毒性や低ナトリウム血症のリスクがあることに注意が必要です。高齢者における多剤併用、加齢に伴う体組成の変化、デスモプレシンに対する薬力学的感受性の増加などが、リスク要因として挙げられています。
私の臨床では、デスモプレシンを処方する際には、必ず腎機能検査や血清ナトリウム値のモニタリングを行い、最小有効量から開始するようにしています。また、水分制限の重要性についても患者さんに十分に説明することが欠かせません。
夜間頻尿の最新治療アプローチ
夜間頻尿の治療は、その原因に応じて異なるアプローチが必要です。まずは原因を明らかにするために、排尿日誌をつけることをお勧めします。
排尿日誌は、朝起きてから翌日の朝まで、排尿した時刻と排尿量を記録するものです。これにより、1回の排尿量(膀胱容量)と排尿回数を知ることができ、おおよその原因を特定できます。
夜間多尿が原因の場合は、まず基礎疾患(糖尿病、高血圧、心疾患など)の治療が重要です。また、夕方以降の水分摂取を控えることも効果的です。最近では夜間の尿量を抑える薬(デスモプレシン)が使われるようになりました。
膀胱容量の減少が原因の場合、過活動膀胱には抗コリン薬やβ3作動薬を、前立腺肥大症にはα1遮断薬、PDE5阻害薬、5α還元酵素阻害薬を症状に合わせて処方します。
睡眠障害による夜間頻尿には、睡眠薬の内服も有効ですが、前述のように適切な就寝時刻の調整や、睡眠環境の整備、生活リズムの改善も重要です。
温灸治療など代替療法の可能性
興味深いことに、夜間頻尿に対する代替療法の研究も進んでいます。例えば、温灸治療の効果を検証したランダム化比較試験では、下腹部の中極穴への温灸治療が夜間頻尿に効果を示したという報告があります。
この研究では、夜間頻尿を有し薬物療法に抵抗性を示す患者を対象に、実際の温灸群とsham温灸群(十分な温度が上昇しない対照群)に分けて比較しました。その結果、温灸群では治療前と比較して夜間排尿回数の有意な減少が見られたのです。
中極穴への温熱刺激が夜間睡眠中の排尿回数を減少させる可能性が示唆されており、薬物療法と併用できる補完的なアプローチとして検討の価値があります。
まとめ:夜間頻尿は諦めずに適切な対策を
夜間頻尿のメカニズムは、夜間多尿、膀胱蓄尿障害、睡眠障害の3つの主要因に分類できます。最新の研究では、アルギニンバソプレシン(AVP)の役割や膀胱からの水分再吸収という新たな知見が明らかになってきました。
治療においては、原因に応じたアプローチが重要です。夜間多尿には水分摂取の調整やデスモプレシン、膀胱蓄尿障害には抗コリン薬やα1遮断薬などの薬物療法、睡眠障害には就寝時刻の調整や睡眠環境の改善が効果的です。
夜間頻尿は加齢とともに増加する症状ですが、「年だから仕方ない」と諦めるのではなく、適切な診断と治療を受けることで改善が期待できます。
質の高い睡眠は健康の基本です。夜間頻尿でお悩みの方は、ぜひ泌尿器科を受診して、あなたに合った治療法を相談してみてください。
夜間頻尿のメカニズムを理解し、適切な対策を講じることで、より質の高い睡眠と生活を取り戻すことができるのです。

〈著者情報〉
泌尿器日帰り手術クリニック
uMIST東京代官山 -aging care plus-
院長 斎藤 恵介