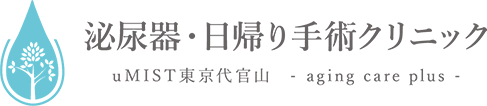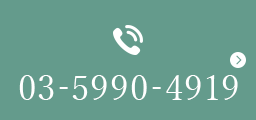女性ホルモン減少がもたらす夜間頻尿のメカニズム
夜中に何度もトイレに起きることで睡眠が分断され、日中の疲労感が増す。
この症状に悩む女性は少なくありません。特に40代後半から50代にかけて、「以前より明らかにトイレが近くなった」と感じる方が増えてきます。この現象は単なる加齢だけでなく、女性ホルモンの減少が大きく関わっているのです。
夜間頻尿とは、夜間に1回以上排尿のために目覚める状態を指します。国際排泄抑制学会の定義によれば、睡眠の前後に睡眠を挟んだ、本来の睡眠時間中に排尿することを意味します。一般的には夜間に2回未満の排尿は正常とみなされることが多いですが、それを超える場合は医学的な問題を考慮する必要があります。
更年期を迎えると、女性の体内ではエストロゲンの分泌量が急激に減少します。このホルモンバランスの変化が、排尿に関わる様々な組織に影響を及ぼすのです。

目次
エストロゲン減少が膀胱と尿道に与える影響
エストロゲンには、膀胱や尿道の粘膜を健康に保つ重要な役割があります。このホルモンが減少すると、粘膜が薄くなり乾燥しやすくなります。その結果、膀胱が過敏になり、少量の尿でも強い尿意を感じるようになるのです。
閉経前は、エストロゲンの作用で腟上皮細胞はグリコーゲンを多く含み、腟内の自浄作用が保たれています。しかし閉経後にエストロゲンが低下すると、腟の粘膜が薄くなり、細菌感染のリスクが高まります。これが尿路感染症を引き起こし、頻尿の原因となることもあるのです。
さらに、エストロゲンの減少は骨盤底筋群の弱体化にも関与します。この筋肉群は膀胱や尿道を支える役割を担っており、弱くなると膀胱の安定性が損なわれ、夜間頻尿の一因となります。
夜間多尿のホルモン的メカニズム
夜間頻尿の原因は、大きく分けて「夜間多尿」と「夜間膀胱容量低下」の二つがあります。
夜間多尿とは、夜間の尿産生量が増加する状態です。通常、健康な若年者では夜間の尿量は24時間尿量の約14%程度ですが、高齢者では約34%にまで増加します。
この変化には、抗利尿ホルモン(ADH)の分泌パターンの乱れが関係しています。ADHは腎臓での水分再吸収を促進するホルモンで、通常は夜間に分泌量が増加して尿量を減らす働きをします。しかし、加齢や更年期に伴い、このADHの夜間分泌が低下することで、夜間の尿量が増えてしまうのです。
女性ホルモンの減少は、このADHの分泌リズムにも影響を与えることが分かっています。エストロゲンとADHの相互作用が乱れることで、夜間の尿量調節機能が低下するのです。
夜間頻尿の原因と分類
夜間頻尿の原因を正確に把握することは、効果的な対策の第一歩です。
泌尿器科学的には、夜間頻尿は主に4つのカテゴリーに分類されます。夜間多尿(NP)、夜間膀胱容量低下(NBC)、混合型(NPと低NBCの組み合わせ)、そして全身性多尿です。これらは24時間排尿日誌の分析から判別可能であり、それぞれ異なるアプローチで対処する必要があります。
夜間多尿(Nocturnal Polyuria)
夜間多尿は、夜間の尿産生が過剰になる状態です。日中の尿産生減少と夜間の尿産生増加が相殺され、24時間尿量は正常のままですが、夜間の尿量が増加します。
夜間多尿の主な原因としては、うっ血性心不全、糖尿病、閉塞性睡眠時無呼吸症、ADH分泌の概日リズム喪失などが挙げられます。特に閉塞性睡眠時無呼吸症は、血漿心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)レベルの上昇を介して腎臓からのナトリウムと水の排泄を増加させ、夜間多尿を引き起こすことがあります。
女性の場合、更年期以降はADH分泌の日内変動が乱れやすくなります。これにより、本来夜間に上昇するはずのADH濃度が十分に上がらず、尿の濃縮が不十分になり、夜間の尿量が増加するのです。
夜間膀胱容量低下(Decreased Nocturnal Bladder Capacity)
夜間膀胱容量低下は、夜間に膀胱が十分な尿を保持できなくなる状態です。機能的膀胱容量(FBC)の低下とNBCの低下の2つのタイプに大別されます。
NBCが減少する原因としては、膀胱下閉塞、神経因性膀胱、膀胱炎、膀胱がんなどが考えられます。女性の場合、エストロゲン減少による膀胱や尿道の粘膜萎縮が、膀胱容量の低下や過活動膀胱の原因となることがあります。
更年期以降の女性では、骨盤底筋の弱化も膀胱容量低下に関与します。出産経験や加齢による骨盤底筋の弛緩は、膀胱の支持力を低下させ、少量の尿でも尿意を感じやすくなるのです。
更年期女性の夜間頻尿対策
夜間頻尿は単なる不快な症状ではなく、睡眠の質を著しく低下させ、日中のパフォーマンスにも影響を及ぼす重要な問題です。
更年期以降の女性における夜間頻尿の対策は、その原因に応じて適切なアプローチを選択することが重要です。ホルモンバランスの変化、骨盤底筋の弱化、生活習慣など、多角的な視点からの対策が効果的です。
当院ではインティマレーザーにてエストロゲン減少により薄くなった尿道粘膜や膣粘膜を再生する治療を行っています。
尿道内の粘膜を改善することで、尿漏れを軽減、膣内を改善することで閉経後尿路性器症候群で起こる違和感や痛み、膀胱脱や反復性する膀胱炎など多岐に渡る諸症状を改善していきます。
ホルモン補充療法(HRT)の可能性
女性ホルモン減少が夜間頻尿の主な原因である場合、ホルモン補充療法(HRT)が効果的な選択肢となります。エストロゲンを補充することで、尿道や膀胱の粘膜を健康に保ち、感染リスクを低減させる効果が期待できます。
HRTは婦人科医との相談のもとで行われるべき治療法です。更年期症状の一つである頻尿の緩和に役立つことがありますが、乳がんや子宮がんのリスク、心血管系への影響など、個々の健康状態に応じたリスク評価が必要です。
特に、エストロゲン単独ではなく、子宮を摘出していない女性の場合は黄体ホルモン(プロゲスチン)を併用して、子宮がんのリスクを回避する必要があります。
骨盤底筋トレーニングの効果
骨盤底筋は膀胱や尿道などの臓器を下から支えている筋肉群です。この筋肉を鍛えることで、膀胱の安定性が向上し、尿意を我慢する力が強くなります。
骨盤底筋トレーニングは、腹圧性尿失禁だけでなく、切迫性、混合性の尿失禁にも効果があります。さらに、このトレーニングは膀胱周辺の血流も改善するため、夜間頻尿の改善にも寄与します。
基本的な骨盤底筋トレーニングは、肛門と腟を締める意識で行います。あおむけに寝て膝を立て、お尻を持ち上げた状態で肛門と腟を5秒間締め、その後力を抜くというエクササイズを5〜10回繰り返します。これを毎日数回、最低3ヶ月は継続することが推奨されます。
生活習慣の見直しと自己管理
夜間頻尿の改善には、日常生活の見直しも重要です。
水分摂取のタイミングを調整することは効果的な対策の一つです。夜間頻尿が気になる場合は、就寝前2〜3時間の水分摂取を控えめにしましょう。ただし、日中の水分摂取を極端に制限すると尿が濃縮され、膀胱刺激の原因になるため、1日1.5〜2リットルを目安に適切な水分補給を心がけてください。
カフェインやアルコールには利尿作用があるため、特に夕方以降の摂取は控えめにすることをお勧めします。また、スパイシーな食品や柑橘系の果物も膀胱を刺激する可能性があるため、就寝前の摂取には注意が必要です。
体を冷やさないことも重要なポイントです。冷えると膀胱周りの筋肉が収縮し、尿意を感じやすくなります。特に下半身を温かく保つよう心がけ、入浴で体を温めることも効果的です。
医学的アプローチと専門医への相談タイミング
セルフケアで改善が見られない場合や、症状が重い場合は、専門医への相談を検討すべきです。
夜間頻尿は単なる不便さだけでなく、健康リスクも伴います。平均年齢76歳の784名を5年間追跡した日本の調査では、夜間頻尿がある人は、骨折や死亡のリスクが高くなると報告されています。夜中にトイレに行く際の転倒リスクや、睡眠不足による日中の活動性低下が原因と考えられます。
排尿日誌の活用と専門的診断
夜間頻尿の正確な診断には、排尿日誌が非常に有用です。排尿量とその時刻を記録することで、夜間多尿なのか膀胱容量の問題なのかを判別できます。
排尿日誌では、夜間頻尿指数(Ni)やNBC指数(NBCi)といった指標を用いて分析します。NiはNUV(夜間尿量)/FBC(機能的膀胱容量)で計算され、NBCiはPNV(予測夜間排尿回数)と実際の夜間排尿回数(ANV)の差として定義されます。
これらの指標を用いることで、夜間頻尿の原因が夜間多尿なのか膀胱容量低下なのか、あるいはその混合型なのかを判別し、適切な治療法を選択することができます。
薬物療法と専門的治療法
夜間多尿に対しては、時間指定利尿薬や抗利尿ホルモン製剤(デスモプレシン)などの薬物療法が検討されることがあります。特にデスモプレシンはADH類似体であり、腎臓での水の再吸収を促進して夜間の尿量を減少させる効果があります。
過活動膀胱による夜間頻尿には、抗コリン薬やβ3作動薬などの薬物療法が用いられることがあります。これらは膀胱の過剰な収縮を抑制し、膀胱容量を増やす効果があります。
閉塞性睡眠時無呼吸症が原因の場合は、持続的経鼻陽圧呼吸療法(CPAP)が効果的です。睡眠の質が改善されるとともに、ANPの分泌が正常化し、夜間多尿が改善することがあります。
参考文献: 文献を見る
これらの治療法は、個々の症状や原因に応じて専門医が適切に選択します。自己判断での薬物使用は避け、必ず医師の指導のもとで行うようにしましょう。
まとめ:更年期以降の排尿トラブルと上手に付き合うために
女性ホルモンの減少と夜間頻尿には密接な関係があります。エストロゲンの低下は、膀胱や尿道の粘膜萎縮、骨盤底筋の弱化、ADH分泌リズムの乱れなど、様々な経路で夜間頻尿を引き起こします。
更年期以降の排尿トラブルに対しては、原因に応じた多角的なアプローチが効果的です。ホルモン補充療法、骨盤底筋トレーニング、生活習慣の見直し、必要に応じた薬物療法など、それぞれの状況に合わせた対策を選択することが重要です。
夜間頻尿は「年齢のせい」と諦めるのではなく、適切な対策で改善できる症状です。症状が気になる場合は、泌尿器科や婦人科などの専門医に相談し、自分に合った対策を見つけることをお勧めします。
質の高い睡眠は健康の基盤です。夜間頻尿を改善することで、睡眠の質が向上し、日中の活動性や生活の質も大きく改善します。更年期以降も快適な毎日を送るために、排尿トラブルと上手に付き合っていきましょう。

〈著者情報〉
泌尿器日帰り手術クリニック
uMIST東京代官山 -aging care plus-
院長 斎藤 恵介