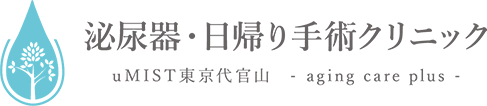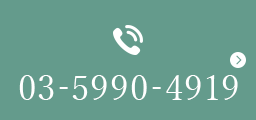夜間頻尿の実態と睡眠への影響
夜間、排尿のために1回以上起きる症状を夜間頻尿と呼びます。健康な方でも夜間に1回起きることはありますが、臨床上問題となるのは夜間2回以上起きる場合です。40歳以上の男女約4,500万人が夜間に1回以上トイレのために起きているというデータがあり、多くの方がこの症状に悩まされています。
特に男性は女性に比べて夜間排尿回数が多い傾向にあり、70歳以上では半数以上、80歳を超えるとほとんどの方が夜間2回以上排尿のために起きているという報告もあります。
夜間頻尿が続くと慢性的な睡眠不足を引き起こし、日中の眠気や疲労感が生じて生活リズムに支障をきたします。さらに、夜間2回以上排尿に起きると、寝ぼけた状態でトイレに行くため、転倒して骨折するリスクも高まります。
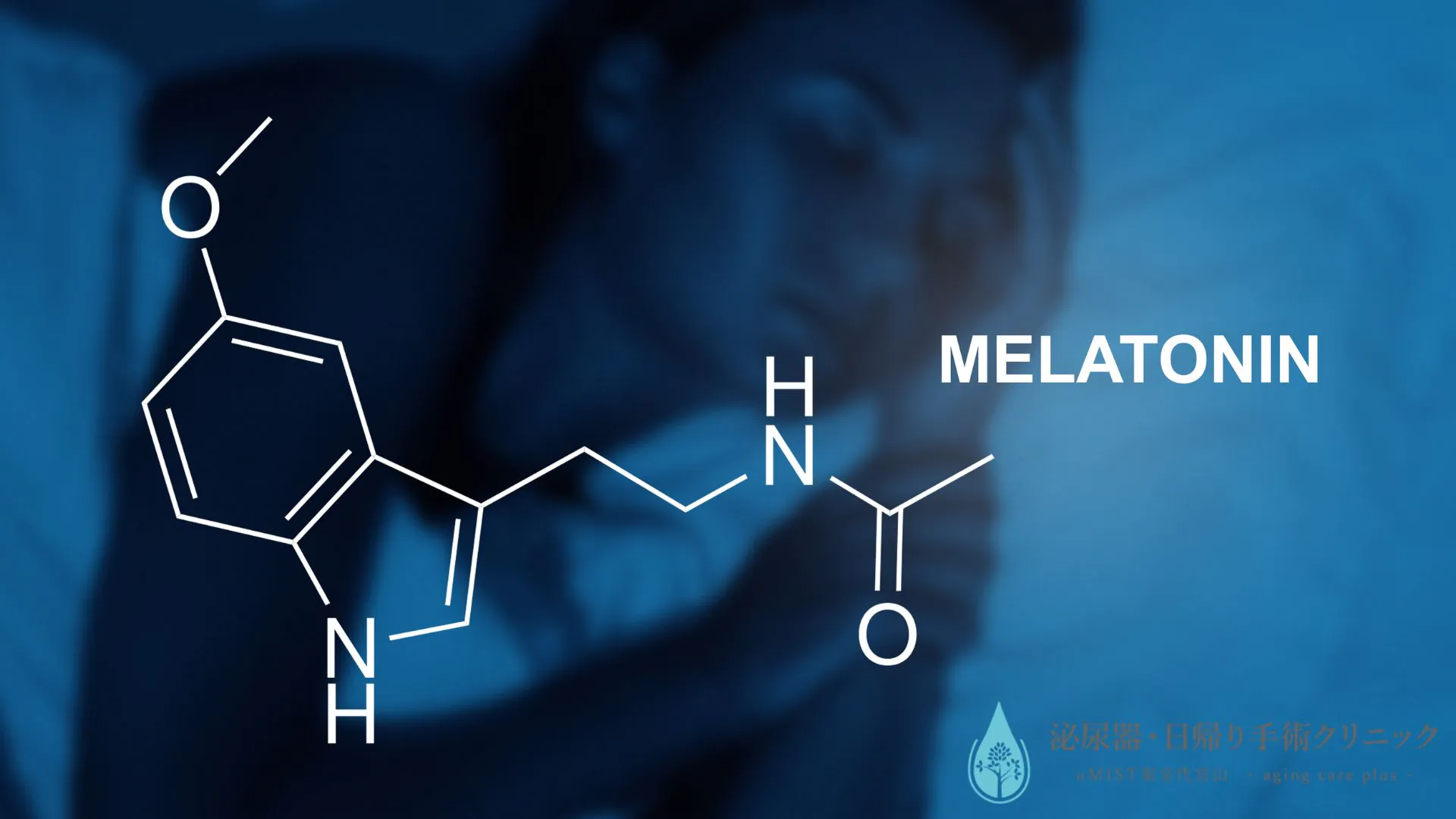
夜間頻尿の主な原因
「夜トイレに起きるのは年のせい」とあきらめている方も多いのではないでしょうか。確かに加齢は要因の一つですが、それ以外にもさまざまな原因があり、適切な治療で改善できる可能性があります。
夜間頻尿の原因は大きく分けて次の3つが挙げられます。
- 多尿および夜間多尿(夜間に尿量が増える)
- 膀胱容量の減少(前立腺肥大症や過活動膀胱など)
- 睡眠障害・不眠
これら3つの原因はそれぞれ治療法が異なるため、まず夜間頻尿の原因を明確にすることが重要です。また、夜間頻尿の患者さんは、これらの原因のうち2つ以上を併せ持っていることが多いのが特徴です。
特に夜間多尿がある場合は、薬物治療だけでは効果が出にくいケースも多く、飲水指導などのセルフケアが中心となることもあります。
メラトニンと排尿の関係性
メラトニンは松果体から分泌される「睡眠ホルモン」として知られていますが、実は排尿機能にも深く関わっています。研究によれば、メラトニンは膀胱機能に直接影響を与え、特に高齢者の夜間頻尿と密接な関係があることが分かってきました。
福井大学の研究では、メラトニンを高齢ラットに静脈投与すると、排尿間隔が有意に延長することが確認されています。興味深いことに、この効果は膀胱内圧や脳波所見に有意な影響を与えずに現れました。
つまり、メラトニンは膀胱の収縮力や排尿圧を変えることなく、膀胱容量を増大させる効果があるのです。これは高齢者の夜間頻尿治療に有用である可能性を示唆しています。
メラトニンの膀胱への作用メカニズム
メラトニンがどのように膀胱機能に影響するのか、そのメカニズムについても研究が進んでいます。膀胱には、アルギニンバソプレシン(AVP)という水分再吸収に関わるホルモンの受容体が存在します。
研究によれば、AVP受容体は排尿筋の緊張調節に直接的な役割を果たしており、メラトニンはこのAVP系に影響を与えることで膀胱機能を調整している可能性があります。
加齢に伴い、膀胱からの尿の恒常的な再吸収機能が低下することが、夜間多尿症や夜間頻尿の一因となると考えられています。メラトニンはこの機能を改善することで、夜間頻尿を軽減する可能性があるのです。
血漿浸透圧の恒常性と夜間頻尿
血漿浸透圧の恒常性維持は、夜間頻尿を理解する上で重要な要素です。血漿浸透圧が上昇すると、視床下部核にある浸透圧受容体がこれを感知し、覚醒中であれば喉の渇きを感じて水分摂取を促します。
しかし、睡眠中は水分摂取ができないため、異なるメカニズムが働きます。視床下部-下垂体-副腎系が、下垂体後葉からのAVP放出と副腎からのアルドステロン放出を調節し、血漿浸透圧を安定化させるのです。
これらのホルモンは腎髄質に作用して尿浸透圧を変動させ、睡眠中の膀胱容量を減少させることで満腹感と排尿衝動による覚醒を抑制します。
膀胱における水分再吸収のメカニズム
近年の研究で、膀胱自体にも水分再吸収機能があることが明らかになってきました。哺乳類尿路上皮のアンブレラ細胞と中間細胞の基底外側表面上に存在するAQP2チャネルは、溶質を含まない水の再吸収の分子経路を提供しています。
このプロセスは、尿路上皮のミネラルコルチコイド受容体、アミロライド感受性内皮型Na+チャネル、および尿素トランスポーターを介した溶質結合水の再吸収によって補完されます。
健康な成人の睡眠中に定期的に超音波測定を行った結果、膀胱容量が客観的に減少していることが確認されています。これは、膀胱膨張によって増強される尿の再吸収を介して夜間の膀胱容量を調節し、満腹感を遅らせるメカニズムが存在することを示唆しています。
加齢に伴い、この膀胱からの尿の恒常的な再吸収機能が低下することが、夜間多尿症や夜間頻尿の一因となると考えられています。
メラトニンと夜間頻尿の治療アプローチ
メラトニンと夜間頻尿の関係性が明らかになるにつれ、新たな治療アプローチの可能性が広がっています。メラトニンを活用した夜間頻尿の改善策としては、以下のような方法が考えられます。
メラトニン分泌を促す生活習慣の改善
自然なメラトニン分泌を促すためには、日常生活の中でいくつかの工夫が効果的です。午前中に日光を浴びることは、体内時計をリセットし、夜間のメラトニン分泌を促進します。太陽の光を浴びると日中はメラトニン分泌が抑制され、眠気が取れるとともに、体のリズムが整い、夜の安眠につながります。
また、夕方以降のカフェイン摂取を控え、就寝前のブルーライト(スマートフォンやタブレットなどの画面から発せられる光)を避けることも重要です。ブルーライトはメラトニン分泌を抑制するため、就寝2時間前からはこれらのデバイスの使用を控えることが望ましいでしょう。
食事からのアプローチ
食事内容も夜間頻尿に影響を与えることが研究で明らかになっています。果物や野菜の摂取量が多い人(1日1000キロカロリーあたり350グラム以上)は、適度な摂取量の人(1日1000キロカロリーあたり250〜350グラム)よりも頻尿・尿意切迫感、夜間頻尿が少ないという報告があります。
特に色の濃い葉物野菜の摂取量が多い人(1日1000キロカロリーあたり50グラム以上)は、中程度の摂取量の人(1日1000キロカロリーあたり25〜50グラム)よりも症状の訴えが有意に少ないことがわかっています。
また、ナトリウム(塩分)の摂取量も夜間頻尿に大きく影響します。1日の塩分摂取量を10.8グラムから8.0グラムに減らした人は夜間頻尿が有意に減少したのに対し、塩分摂取量が9.6グラムから11グラムに増えた人は夜間の排尿が増加したというデータもあります。
このように、メラトニン分泌を考慮した生活習慣の改善と、適切な食事管理を組み合わせることで、夜間頻尿の症状改善が期待できるのです。
代表的な研究例をいくつかご紹介致します。
ケース1
高塩分摂取の夜間頻尿患者
塩分制限群では夜間排尿回数・頻尿の改善が認められた。
ただし、24時間尿量を完全に追跡したかどうかや長期フォローについては限定的という記載。
ケース2
「TOP-STAR」研究(多施設無作為化オープンラベル試験)
夜間排尿頻度を下げるための塩分低減効果を検証する試みの論文が公表予備・概要段階で確認されており、意図として「過剰ナトリウム摂取 → 夜間排尿」仮説を検証
夜間頻尿改善のためのセルフケア
夜間頻尿の改善には、医療機関での治療だけでなく、日常生活でのセルフケアも重要です。以下に、自分でできる効果的なセルフケア方法をご紹介します。
適切な水分摂取と排尿管理
水分摂取量と尿量には強い相関関係があります。就寝前2〜3時間は水分摂取を控えめにすることで、夜間の尿量を減らすことができます。ただし、日中は適切な水分補給を心がけ、脱水状態にならないよう注意しましょう。
また、コーヒーや緑茶などのカフェインを含む飲み物やアルコールには利尿作用があるため、夕方以降は控えることをおすすめします。日中に適量飲むようにし、夜間の頻尿を防ぎましょう。
適度な運動と生活リズムの調整
夕方の運動はお勧めです。追加して30分くらいの下肢挙上や下肢のストレッチ、青竹ふみなど、第二の心臓と言われるふくらはぎの運動で抹消に溜まった余剰な水分を起きているうちに尿に変換する行動や運動が重要です。
運動をすることで、ほどよい疲労感も得られ、ストレス解消になります。また、体温が下がると入眠しやすくなるため、運動で体温を少し上げておくと、寝るころには体温が下がり、寝入りがよくなります。
昼寝をする場合は、午後1〜3時ごろまでに30分以内にすることがおすすめです。ただし、30分以上の昼寝が認知症につながる可能性もある論文も発表されていることから、おすすめと結論を出すのは難しいとも言えます。
自分の排尿状態を知る
夜間頻尿の治療で最も大切なことは、自分の排尿状態を把握し、夜間多尿がないかなど夜間頻尿の原因を知ることです。排尿の記録(排尿日誌)をつけることで、夜間頻尿の原因を特定する重要な情報が得られます。
排尿時に計量カップなどを用意して、日中の尿量と夜間の尿量を分けて測定することが役立ちます。24時間分の尿量を量り、時刻とともに記録します。外出しない日に行うことが理想ですが、難しい場合は飲水量とトイレの回数をメモするだけでも役立ちます。
夜間の排尿において、毎回十分な排尿量がある場合(だいたい200-300ml/回150-200ml/回日中)(夜間150-300ml/夜間)は多尿もしくは夜間多尿による夜間頻尿、また1回排尿量(膀胱に溜めることができる膀胱容量)が少ない場合(100ml/回以下)なら膀胱容量の減少による夜間頻尿と考えられます。
このように自分の排尿パターンを知ることで、より効果的な対策を講じることができるのです。
まとめ:メラトニンと夜間頻尿の関係性から考える対策
夜間頻尿は単なる加齢現象ではなく、メラトニンをはじめとする様々なホルモンバランスや生理機能の変化が関与する複雑な症状です。メラトニンは睡眠ホルモンとしてだけでなく、膀胱機能にも直接影響を与え、特に高齢者の夜間頻尿と密接な関係があることが研究で明らかになっています。
メラトニンは膀胱容量を増大させる効果があり、これにより夜間頻尿を改善できる可能性があります。また、膀胱自体にも水分再吸収機能があり、この機能が加齢とともに低下することが夜間頻尿の一因となっています。
夜間頻尿の改善には、メラトニン分泌を促す生活習慣の改善(朝の日光浴、夕方以降のカフェイン・ブルーライト制限など)、適切な食事管理(果物・野菜の摂取、減塩など)、そして適切な水分摂取と排尿管理が重要です。
自分の排尿状態を知るために排尿日誌をつけることも効果的な対策の一つです。症状が改善しない場合は、専門医に相談し、適切な治療を受けることをおすすめします。
夜間頻尿は生活の質を大きく低下させる症状ですが、メラトニンと排尿の関係性に着目した対策を講じることで、より良い睡眠と健康的な生活を取り戻すことができるでしょう。

〈著者情報〉
泌尿器日帰り手術クリニック
uMIST東京代官山 -aging care plus-
院長 斎藤 恵介