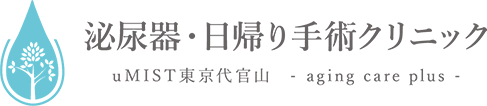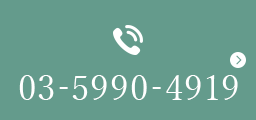サルコペニアとは?加齢による筋肉減少の正体
サルコペニアという言葉をご存知でしょうか。これは加齢によって全身の筋力や筋肉量が低下した状態を指します。語源はギリシャ語で、「サルコ(筋肉)」と「ぺニア(喪失)」という言葉を組み合わせた造語です。
サルコペニアは高齢者に多く見られる現象で、75~79歳の男女のおよそ2割がサルコペニアに該当するといわれています。ただ、実は20~30歳頃にはすでに進行が始まり、生涯にわたって進行し続けるのです。

目次
サルコペニアの症状と影響~見逃せない7つのサイン
サルコペニアになると、日常生活のさまざまな場面で支障が出始めます。以下の症状に心当たりがないか、チェックしてみましょう。
転びやすくなる、頻繁につまずくといった症状は要注意です。歩くスピードが遅くなり、青信号の間に横断歩道を渡りきれなくなることもあります。
握力が低下してペットボトルのキャップが開けにくくなったり、短距離の移動や立っているだけでも疲れやすくなったりします。また、手すりにつかまらないと階段を上がるのが困難になることも。
特に注目すべきは、サルコペニアと夜間頻尿の関連性です。研究によれば、高齢女性の夜間排尿頻度と股関節外転筋力の弱さには有意な関連があることがわかっています。夜間排尿回数が夜間1回以上の頻度は28.1%であり、この頻度は股関節外転筋力の四分位値と逆相関しているのです。
サルコペニアは単なる筋力低下ではなく、全身の健康状態に影響を及ぼす可能性があります。早期発見と適切な対策が重要です。
夜間頻尿とサルコペニアの意外な関係
夜間頻尿は高齢者によく見られる現象であり、生活の質の低下と関連しています。これは多因子性疾患ですが、骨格筋の虚弱性、特に下体幹および股関節部の筋力低下が女性におけるリスク因子となる可能性があります。
研究では、平均年齢67.4±5.2歳の1,207名の高齢女性を対象に、1週間の睡眠日誌を用いて夜間排尿頻度を評価し、筋力低下、骨格筋指数、サルコペニア、および身体能力との関連を調査しました。
その結果、股関節外転筋力が夜間頻尿の独立した逆因子であることが示されました(オッズ比0.75)。つまり、股関節外転筋力が弱いほど、夜間頻尿のリスクが高まるのです。
一方で、膝伸展筋力や股関節屈曲筋力とは有意な関連は認められませんでした。また、身体能力、骨格筋指数、サルコペニア自体は夜間頻尿と有意な関連を示さなかったことも興味深い点です。
自宅でできるサルコペニアのセルフチェック方法
サルコペニアは自分でチェックできるのでしょうか?
実は、いくつかの簡単な方法で自宅でもサルコペニアの可能性を評価することができます。ここでは、専門的な機器がなくても実施できる7つの指標をご紹介します。
1. 指輪っかテスト
サルコペニアは、ふくらはぎ周囲の長さを測る「指輪っかテスト」という簡単な検査法により自分でチェックすることができます。
ふくらはぎの一番太い部分が、両手の親指と人差し指で作った輪よりも小さく隙間ができれば、サルコペニアである可能性が高いと考えられます。指輪っかテストでは、体格にある程度比例する手の大きさを用いることで、ふくらはぎの筋肉量が体格に比べて維持されているかを自己評価できます。
日本の高齢者を対象とした研究では、指輪っかテストで隙間ができる方は、サルコペニアの有病率が高くなることがわかっています。隙間ができる方では、サルコペニアの危険度が6.6倍多く含まれ、2年間で新たにサルコペニアを発症するリスクが3.4倍高くなる結果が示されています。
2. 開眼片脚立位テスト
開眼片脚立位テストは、バランス能力と下肢筋力を評価する簡単な方法です。壁の近くなど安全な場所で、片足で立ち、その状態をどれだけ維持できるかを測定します。
いずれか片側でも8秒未満となった場合、筋肉の機能が低下している可能性が高いと考えられています。
3. 5回立ち座りテスト
椅子から立ち上がり、再び座るという動作を5回繰り返す時間を測定します。10秒以上かかる場合は、下肢筋力の低下が疑われます。
このテストは下肢の筋力だけでなく、バランス能力や協調性も評価できる総合的な指標です。
4. 握力測定
握力計があれば、筋力の重要な指標である握力を測定できます。サルコペニアの診断基準では、握力が男性28kg未満、女性18kg未満の場合に筋力低下ありと判定されます。
握力計がなくても、ペットボトルのキャップが開けにくい、重い荷物を持つのが困難になったと感じる場合は、握力低下の可能性があります。
5. 歩行速度チェック
6メートルの距離を普通に歩いた時間を測定します。秒速1.0メートル未満(6メートルを6秒以上かけて歩く)場合、身体機能の低下が疑われます。
青信号の間に横断歩道を渡りきれないと感じる場合も、歩行速度の低下を示唆しています。
6. イレブン・チェック
食事や運動、社会参加に関連する11の質問項目からサルコペニアをセルフチェックできる方法です。回答は約1〜2分で完了し、サルコペニアのリスクを総合的に評価できます。
7. 足関節の運動範囲チェック
最新の研究では、歩行中の足関節(足首の関節)の運動範囲の減少が、サルコペニアを有する患者の特徴である可能性が示唆されています。
座った状態で足首をできるだけ上下に動かし、その可動域が制限されていると感じる場合は、サルコペニアの可能性を考慮する必要があります。
サルコペニアのタイプと原因
サルコペニアには、加齢による「一次性サルコペニア」と、加齢が原因でない「二次性サルコペニア」の2つのタイプに分類されます。
一次性サルコペニアは、加齢のほかに明確な原因はありません。「加齢性サルコペニア」とも呼ばれています。
一方、二次性サルコペニアは、加齢以外の要因をはらんでいるケースです。その要因ごとに、さらに3つに分類されます。
活動量に関するサルコペニアは、寝たきりや運動不足が要因となって筋肉量が減ることで起こります。デスクワークが中心で日頃の活動量が少ない方は、活動量が原因であるサルコペニアになってしまう可能性があるでしょう。
疾病に関するサルコペニアは、心疾患やがん、外傷など病気やケガが要因となって引き起こされます。特に糖尿病患者はサルコペニアのリスクが高いことが知られています。
また、栄養に関するサルコペニアは、エネルギーやタンパク質不足などが原因となります。また、服用している薬の副作用によって、食欲不振を起こしている方も該当します。
二次性サルコペニアの場合、その原因を取り除くことで症状改善が見込めます。そのためにも、どのような原因でサルコペニアになってしまっているのかを把握しておくことが大切です。
若年層でもサルコペニアになる可能性があることも覚えておきましょう。若い人でも病気や低活動、低栄養などが原因となり、二次性サルコペニアになる可能性があるのです。
サルコペニアの診断基準
サルコペニアの診断は、筋肉量、筋力、身体機能の3つの要素から総合的に判断されます。
握力低下(男性28kg未満、女性18kg未満)、歩行速度低下(1.0m/秒以下)のいずれかまたは両者を満たし、骨格筋量指数(SMI)が男女別のカットオフ値未満の場合にサルコペニアと診断されます。
四肢の筋肉量の合計を身長(m)の2乗で割った値を骨格筋量指数(Skeletal Muscle mass Index:SMI)と呼び、筋肉の量の評価値として用います。
日本サルコペニア・フレイル学会では、骨格筋量や歩行速度を測定せずにサルコペニアの可能性が診断できる基準も作成されています。ただし、確定診断には「筋力:握力」「身体機能:歩行速度」「骨格筋量」の測定が必須です。
さらに詳細な分類として、以下の4つのカテゴリーも提唱されています。
- 正常:握力、歩行速度正常・筋量正常
- プレサルコペニア:握力、歩行速度正常・筋量低下
- サルコペニア:握力、歩行速度低下・筋量低下
- ダイナペニア:握力、歩行速度低下・筋量正常
すなわち、握力や歩行速度の低下がなくても筋量(SMI)の低下しているかた(プレサルコペニア)や、握力や歩行速度の低下があっても筋量(SMI)が正常なかた(ダイナぺニア)があります。
ダイナぺニアでは筋肉の量は正常でも脂肪の浸潤など筋肉の質の低下が、筋力機能の低下を引き起こすとされています。
参考文献: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ggi.13761
サルコペニアと骨粗鬆症の関係
サルコペニアと骨粗鬆症には密接な関連があります。股関節骨折を発症した高齢白人女性患者の半数近くが骨粗鬆症とサルコペニア両方を有していたとの報告があります。
高齢男性においても同様にサルコペニアと低骨密度(骨粗鬆症)が相関するとの報告があります。
高齢者の骨粗鬆症や骨折後の管理はオステオサルコペニアとして、骨と筋肉の双方を対象にしていかなくてはなりません。
サルコペニアも骨粗鬆症もオステオサルコペニアも、DXAを使用して骨と筋肉、両方の検査を同時に行うことが可能です。
サルコペニアの予防と改善方法
サルコペニアの予防・改善には、主に運動と栄養の2つのアプローチが重要です。
抵抗運動などを基本とした運動は筋量、筋力、運動能力に対して概ね有効です。
日本人では大腿部の筋量と筋質に男女差があり、高齢男性ほど量も質も加速度的に低下することがわかっています。筋力の発揮には筋量も筋質も重要な働きをしています。
60歳以上のサルコペニアにおいては、運動は、身体能力に大きな影響を示し、筋力に中程度の影響を示しました。一方で筋量に対しては一定の影響はありませんでした。
蛋白補給などの栄養も有効です。特に良質なタンパク質の摂取は筋肉の合成を促進します。
サルコペニアの予防・改善には、個々の状況に応じた適切な運動と栄養の組み合わせが重要です。専門家に相談しながら、自分に合った対策を見つけていきましょう。
当院では、テストステロン補充療法+スターフォーマー(多岐に渡る部位に1分間に5万回の筋肉収縮を起こす治療)の併用で高い効果が出ています。
合わせて読みたい: 当院のスターフォーマー治療について
まとめ:サルコペニアの早期発見と対策の重要性
サルコペニアは加齢に伴う筋肉量・筋力の低下であり、日常生活に様々な影響を及ぼします。20代から始まるこの変化は、放置すれば転倒リスクの増加や生活の質の低下につながります。
本記事でご紹介した7つのセルフチェック方法(指輪っかテスト、開眼片脚立位テスト、5回立ち座りテスト、握力測定、歩行速度チェック、イレブン・チェック、足関節の運動範囲チェック)を活用して、ご自身の状態を定期的に確認してみてください。
サルコペニアは早期発見と適切な対策により、進行を遅らせたり、改善したりすることが可能です。運動と栄養を中心とした生活習慣の改善に取り組み、健康的な筋肉を維持していきましょう。
気になる症状がある場合は、医療機関での専門的な評価と指導を受けることをお勧めします。

〈著者情報〉
泌尿器日帰り手術クリニック
uMIST東京代官山 -aging care plus-
院長 斎藤 恵介