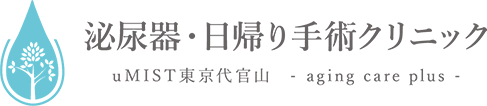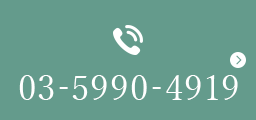骨盤臓器脱とは?〜女性の生活を妨げる隠れた疾患
骨盤臓器脱は、骨盤底筋群の機能異常によって骨盤内臓器が下垂し、膣から脱出してしまう疾患です。子宮や膀胱、直腸といった臓器が本来あるべき位置から下がり、時には膣の外にまで出てくることもあります。
この疾患は、出産や加齢、肥満などによって骨盤底が弱くなることで発症します。骨盤底は複数の筋肉と靭帯で構成され、骨盤内臓器を支える「ハンモック」のような役割を果たしています。この支持機構が弱まると、腹圧がかかった際に臓器が下方へ押し出されてしまうのです。
出産を経験した女性のおよそ50%が何らかの骨盤臓器脱を抱えているといわれており、決して珍しい疾患ではありません。しかし、恥ずかしさから医療機関を受診せず、長年にわたって不快な症状を我慢している方も少なくありません。

目次
骨盤臓器脱の種類と症状〜何が起きているのか
骨盤臓器脱は、下がってくる臓器によって呼び方が異なります。それぞれの種類と特徴的な症状を見ていきましょう。
膀胱脱
膀胱脱は、膀胱が膣の前壁を押し下げて膣内や膣外に脱出した状態です。膣の外に丸くて柔らかいピンポン玉のようなものが触れることが多く、以下のような症状が現れます。
- 頻尿(トイレが近い)
- 残尿感(尿が残る感じがする)
- 排尿困難(尿が出しづらい)
- 切迫感(急にトイレに行きたくなる)
- 反復性膀胱炎
特に症状が進行すると、排尿するために膣内に指を入れて膀胱を押し上げなければならないこともあります。これは「スプリント」と呼ばれ、日常生活に大きな支障をきたします。
子宮脱
子宮脱は、子宮が下垂して膣から脱出する状態です。腟の外に少し硬く丸いものを触れることが多く、時に下着とすれて出血することもあります。主な症状には以下のようなものがあります。
- 下腹部や腟の中に何かが降りてきた感じ
- 腰痛や下腹部痛
- 性交痛
- 歩行時の違和感や痛み
子宮脱が進行すると、完全に膣外に脱出して日常生活が著しく制限されることもあります。
直腸脱
直腸脱は、直腸が膣の後壁を押し出して膣内に突出した状態です。膣の後ろのほうに丸くて柔らかいピンポン玉のようなものが触れることが多く、排便に関する症状が特徴的です。
- 排便困難(気張っても便が出にくい)
- 残便感(便が残っている感じですっきりしない)
- 排便後の下着汚染
直腸脱が重度になると、指で膣後壁を押さえなければ排便できなくなることもあります。
小腸脱
小腸脱は、小腸が膣上部(膣円蓋)から膣内に突出した状態です。他の脱出と比べて診断が難しく、症状も類似していることが多いです。
これらの症状は単独で現れることもありますが、複数の臓器が同時に脱出することも珍しくありません。また、症状は朝よりも夕方に悪化する傾向があり、立ち仕事や長時間の歩行後に特に強くなります。
骨盤臓器脱の原因と危険因子〜なぜ起こるのか
骨盤臓器脱の原因は完全には解明されていませんが、骨盤底筋群の機能異常が主な要因とされています。特に以下のような危険因子が関与していることがわかっています。
出産による影響
出産は骨盤臓器脱の最も重要な危険因子です。特に経腟分娩では、分娩時の骨盤底筋や靭帯の損傷が起こります。出産後にいったん回復しても、加齢とともに筋力が低下すると、以前傷ついた部分が臓器を支えきれなくなります。
出産回数が多いほどリスクは高まりますが、帝王切開でも骨盤臓器脱のリスクはあります。妊娠自体が骨盤底に負担をかけるためです。
加齢と閉経後のホルモン変化
年齢を重ねるにつれて骨盤底筋の筋力は自然に低下します。特に閉経後はエストロゲンの減少により、骨盤底の筋肉や結合組織が弱くなります。これが骨盤臓器脱の発症や進行を促進する要因となります。
腹圧上昇を伴う生活習慣
慢性的に腹圧が上昇する生活習慣も骨盤臓器脱のリスクを高めます。
- 慢性的な咳(喫煙、慢性気管支炎など)
- 便秘(排便時のいきみ)
- 重い物の持ち上げ(職業的要因)
- 肥満
これらの要因は骨盤底に継続的な圧力をかけ、支持組織を徐々に弱めていきます。
遺伝的要因
骨盤臓器脱には遺伝的な素因も関与しています。コラーゲンの質や量に影響する遺伝的な違いが、骨盤底の強度に影響を与える可能性があります。家族に骨盤臓器脱の方がいる場合、リスクが高まることが知られています。
これらの危険因子が複合的に作用することで、骨盤臓器脱のリスクは高まります。特に出産経験のある女性が加齢とともに症状を自覚することが多いのはこのためです。
骨盤臓器脱の診断〜専門医による評価
骨盤臓器脱の診断は、詳細な問診と身体診察が基本となります。症状の種類や程度、日常生活への影響などを詳しく聞き取った上で、適切な検査を行います。
問診と症状評価
まず医師は以下のような点について詳しく質問します。
- 下垂感や違和感の有無と程度
- 排尿症状(頻尿、残尿感、排尿困難など)
- 排便症状(便秘、残便感など)
- 性交時の症状(痛みなど)
- 日常生活への影響
- 出産歴や手術歴
症状の評価には標準化された質問票が用いられることもあります。例えば、骨盤底障害コンソーシアム(PFDC)が開発したIMPACT(患者報告による骨盤底苦情の初期測定ツール)などです。
身体診察
内診台での診察では、安静時と腹圧をかけた時(いきんだ時)の骨盤臓器の位置を評価します。膣鏡を用いて膣粘膜の状態を確認したり、指を使って骨盤底筋の収縮力や痛みの有無を調べたりします。
骨盤臓器脱の程度は、国際的な基準であるPOP-Q(Pelvic Organ Prolapse Quantification)システムを用いて評価されることが多いです。これにより、脱出の程度を客観的に記録し、経過観察や治療効果の判定に役立てます。
追加検査
必要に応じて以下のような追加検査が行われることもあります。
- 尿流動態検査:膀胱と尿道の機能を評価
- 排便造影検査:排便時の直腸や骨盤底の動きを評価
- MRI検査:骨盤内臓器の位置関係を詳細に評価
これらの検査は、症状が複雑な場合や、手術治療を検討する際に特に重要となります。
骨盤臓器脱の診断は泌尿器科医、婦人科医、大腸肛門科医など複数の専門医が関わることもあります。それぞれの専門分野から評価することで、より適切な治療計画を立てることができます。
骨盤臓器脱の保存的治療〜手術以外の選択肢
骨盤臓器脱の治療は、症状の程度や患者さんの希望に応じて選択します。軽度から中等度の症状であれば、まずは保存的治療から始めることが一般的です。
生活習慣の改善
骨盤臓器脱の症状を軽減し、進行を予防するために以下のような生活習慣の改善が推奨されます。
- 体重管理:肥満の方は体重を3~5%減らすだけでも症状が約50%改善することがあります
- 便秘の解消:食物繊維の摂取や適切な水分補給
- 喫煙の中止:慢性的な咳を減らし、組織の修復能力を高める
- 重い物の持ち上げ方の工夫:腹圧をかけないよう注意
これらの生活習慣の改善は、どの治療法を選択する場合でも基本となる重要な要素です。
骨盤底筋トレーニング(ケーゲル体操)
骨盤底筋トレーニングは、骨盤底の筋力を強化し、臓器の支持機能を改善するための運動療法です。正しく行えば、軽度の骨盤臓器脱の症状改善に効果があります。
基本的なトレーニング方法は以下の通りです。
- 骨盤底筋を5秒間収縮させる(尿を我慢するような感覚)
- 5秒間リラックスする
- これを10回繰り返し、1日3セット行う
ただし、正しい筋肉を使えているか確認するために、理学療法士などの専門家の指導を受けることが望ましいです。当院には骨盤底ケア専門外来があり、個別指導や集団リハビリも行っています。
ペッサリー
ペッサリーは、膣内に挿入して臓器の脱出を物理的に防ぐ医療機器です。リング状のものが最も一般的ですが、患者さんの状態に合わせて様々な形状やサイズがあります。
ペッサリーのメリットとしては、以下のような点が挙げられます。
- 手術を避けたい方に適している
- 即効性がある
- 取り外し可能で調整できる
- 妊娠希望のある方でも使用可能
一方、定期的な交換や洗浄が必要であり、長期間の使用では膣壁の炎症や潰瘍を引き起こす可能性もあります。当院では2~3ヶ月ごとの交換を基本としていますが、自己管理が可能な方には毎日の着脱方法もお教えしています。
その他の保存的治療
症状に応じて以下のような治療も併用されることがあります。
- 局所エストロゲン療法:閉経後の膣萎縮改善のため
- バイオフィードバック:骨盤底筋の適切な収縮と弛緩を訓練
- 電気刺激療法:骨盤底筋の収縮を促進
保存的治療は、骨盤臓器脱自体を完全に治すものではありませんが、症状の緩和や進行の予防に役立ちます。また、手術に踏み切る前の一時的な対応としても有用です。
骨盤臓器脱の外科的治療〜最新の手術療法
保存的治療で十分な効果が得られない場合や、重度の脱出がある場合には手術治療が検討されます。手術法は患者さんの年齢、症状、活動性、性生活の有無などを考慮して選択します。
従来の経腟手術
経腟的アプローチによる手術は、膣から行うため腹部に傷が残らないメリットがあります。主な術式には以下のようなものがあります。
- 前膣壁形成術:膀胱脱に対する修復術
- 後膣壁形成術:直腸脱に対する修復術
- 膣式子宮全摘術:子宮脱に対する手術
- マンチェスター手術:子宮を温存する修復術
これらの手術は比較的低侵襲ですが、再発率が高いという課題があります。特に複数の臓器が脱出している場合、一部分だけを修復すると他の部位に負担がかかり、別の臓器が脱出することもあります。
メッシュを用いた手術
人工メッシュを用いた手術は、骨盤底の支持組織を強化する目的で行われます。日本では国産メッシュ(ORIHIME)を用いた経腟メッシュ手術(TVM手術)が行われています。
メッシュ手術のメリットは、自己組織だけでは不十分な支持力を人工材料で補強できることです。しかし、メッシュびらん(露出)や収縮、疼痛などの合併症リスクもあります。
なお、欧米では経腟メッシュ手術に関する安全性の懸念から使用が制限されていますが、日本では事前の手術登録などの安全対策のもと継続されています。
腹腔鏡下仙骨固定術
腹腔鏡下仙骨固定術は、腹腔鏡を用いて膣上部を仙骨前面に固定する手術です。メッシュを使用しますが、膣内ではなく腹腔内に留置するため、経腟メッシュ手術とは異なります。
この手術の利点は、解剖学的に正常な位置に臓器を戻すことができ、再発率が低いことです。一方で、技術的に難易度が高く、腹部に小さな傷が複数残ります。
ロボット支援下仙骨固定術
最新の術式として、ロボット支援下仙骨固定術があります。2020年から保険適用となったこの手術は、ダヴィンチと呼ばれる手術支援ロボットを用いて行います。
ロボット支援手術の利点は以下の通りです。
- 3D高解像度視野による精密な操作
- 手振れ防止機能による安定した縫合
- 関節機能を持つ鉗子による複雑な操作
- 狭い骨盤腔での操作性の向上
これらの特徴により、従来の腹腔鏡手術よりもさらに精密な手術が可能となり、合併症リスクの低減や術後の早期回復が期待できます。
閉経後の高齢者に対する手術
性生活がなく、高齢の患者さんに対しては、膣閉鎖術が選択肢となることもあります。この手術は膣の一部または全部を閉じることで臓器の脱出を防ぎます。比較的低侵襲で、再発率も低いのが特徴です。
手術法の選択は、患者さんの状態や希望を十分に考慮して行います。骨盤臓器脱の手術は専門性が高いため、この分野に精通した医師のいる施設での治療が望ましいでしょう。
骨盤臓器脱の予防と日常生活での注意点
骨盤臓器脱は完全に予防することは難しいですが、リスクを減らすための対策はあります。また、すでに症状がある方も、進行を遅らせるための工夫が重要です。
骨盤底筋の定期的な強化
骨盤底筋トレーニングは、治療としてだけでなく予防法としても効果的です。特に出産後の女性は、積極的に取り組むことをお勧めします。
正しいトレーニング方法を身につけるためには、専門家の指導を受けることが理想的です。一度習得すれば、日常生活の中で継続して行うことができます。
適切な体重管理
肥満は骨盤底に過剰な負担をかける主要な要因です。適正体重を維持することで、骨盤臓器脱のリスクを大幅に減らすことができます。
急激なダイエットではなく、バランスの良い食事と適度な運動による健康的な体重管理を心がけましょう。
腹圧上昇を避ける工夫
日常生活では、腹圧の急激な上昇を避ける工夫が大切です。
- 重い物を持ち上げる際は、膝を曲げて腰に負担をかけないようにする
- 便秘を予防するため、十分な水分と食物繊維を摂取する
- 慢性的な咳の原因となる喫煙を避ける
- 排便時に強くいきまないよう注意する
これらの習慣は、骨盤底への負担を軽減し、臓器脱のリスクを下げるのに役立ちます。
閉経後のホルモン管理
閉経後のエストロゲン減少は、骨盤底組織の弱体化を促進します。必要に応じて、局所エストロゲン療法などのホルモン補充を検討することも一つの選択肢です。
ただし、ホルモン療法には他の健康リスクも伴うため、必ず医師と相談の上で判断してください。
定期的な健康チェック
骨盤臓器脱の初期症状に気づいたら、早めに専門医を受診することが重要です。早期の適切な対応により、症状の進行を遅らせることができます。
また、定期的な婦人科検診を受けることで、自覚症状がない初期の変化も発見できる可能性があります。
参考文献:骨盤底機能障害骨盤臓器脱に感する推論
まとめ〜骨盤臓器脱と上手に付き合うために
骨盤臓器脱は、出産や加齢などにより骨盤底が弱まることで発症する疾患です。子宮脱、膀胱脱、直腸脱など、様々な形で現れ、日常生活に大きな影響を与えることがあります。
治療法としては、生活習慣の改善や骨盤底筋トレーニングなどの保存的治療から、ペッサリーの使用、さらには様々な手術療法まで、症状の程度や患者さんの状態に応じた選択肢があります。
特に近年は、ロボット支援下仙骨固定術など、より精密で低侵襲な手術法も普及してきており、治療の選択肢が広がっています。
骨盤臓器脱は決して珍しい疾患ではなく、出産経験のある女性の約半数が何らかの症状を抱えているとされています。しかし、恥ずかしさから受診を躊躇する方も多いのが現状です。
症状に気づいたら、早めに専門医に相談することをお勧めします。適切な治療により、生活の質を大きく改善することができます。また、予防のための生活習慣の改善や骨盤底筋トレーニングは、すべての女性にとって有益な取り組みと言えるでしょう。
骨盤臓器脱は完全に治癒することが難しい場合もありますが、適切な対処法を知り、上手に付き合っていくことで、快適な日常生活を取り戻すことが可能です。

〈著者情報〉
泌尿器日帰り手術クリニック
uMIST東京代官山 -aging care plus-
院長 斎藤 恵介