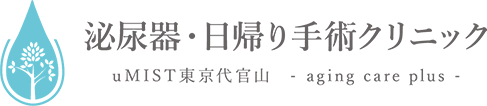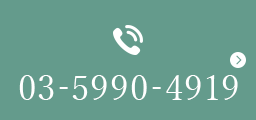睡眠時無呼吸症候群と夜間頻尿の意外な関連性
夜中に何度もトイレに起きてしまう。そんな悩みを抱えている方は少なくありません。単なる加齢現象と諦めていませんか?
実は、夜間頻尿の背後には睡眠時無呼吸症候群が潜んでいる可能性があるのです。この二つの症状は、一見無関係に思えますが、実は深い関連があることが最新の研究で明らかになってきました。
私は泌尿器科医として多くの患者さんの夜間頻尿に対応してきましたが、睡眠時無呼吸症候群との関連を知ることで、治療アプローチが大きく変わることを実感しています。今回は、この二つの症状の関係性と対策について詳しくお伝えします。

目次
夜間頻尿とは?その原因と影響
夜間頻尿とは、夜間の睡眠中に2回以上トイレに行く状態を指します。単に「夜中にトイレに行く回数が多い」という症状ですが、これが続くと睡眠の質が著しく低下し、日中の活動にも支障をきたします。
夜間頻尿の原因は大きく分けて以下の3つに分類されます。
- ・多尿(夜間の尿量が多い)
- ・膀胱容量の減少
- ・睡眠時無呼吸症候群
特に3つ目の「睡眠時無呼吸症候群」と夜間頻尿の関りは、一般的にはあまり知られていません。しかし、睡眠時無呼吸症候群の患者さんの約50%に夜間頻尿が見られるという報告があります。
夜間頻尿は単なる不便さだけでなく、健康への影響も大きいのです。夜間の睡眠が分断されることで、日中の眠気や集中力低下を引き起こします。さらに、暗い中でトイレに行くことによる転倒リスクも高まります。
大腿骨頚部骨折は夜間頻尿を有する方で有意に頻度が高いことも報告されています。長期的には体力低下やうつ状態を引き起こし、生存率の低下にもつながる可能性があるのです。
夜間頻尿の有病率と性差
夜間頻尿は非常に一般的な症状で、全人口の28.5%が罹患しているとされています。年齢別に見ると、50歳未満では16.5%、70歳以上では60%が夜間頻尿を訴えています。
興味深いことに、50歳未満の人口では、夜間頻尿は男性よりも女性に多く見られます。一方、50歳以上になると、男性の夜間頻尿の頻度が急激に増加します。
この性差は、男性の場合は前立腺肥大などの影響が大きいためと考えられています。また、女性の場合は骨盤底筋の弱化や閉経後のホルモン変化が影響していることが知られています。
睡眠時無呼吸症候群の基本知識
睡眠時無呼吸症候群とは、眠っている間に無呼吸状態(呼吸が止まっている状態)が繰り返される病気です。医学的には10秒以上の呼吸停止状態を「無呼吸」と定義し、無呼吸が1時間あたり5回以上、または一晩(7時間の睡眠中)に30回以上あれば、睡眠時無呼吸症候群と診断されます。
この無呼吸状態は寝ている間のことなので、本人はなかなか気付くことができません。そのため、検査や治療を受けていない方が多く、日本でも300万人~400万人の潜在的な患者さんがいると言われています。
睡眠時無呼吸症候群の主な症状には以下のようなものがあります。
- ・大きないびき
- ・日中の強い眠気
- ・起床時の頭痛
- ・集中力の低下
- ・夜間の頻尿
- ・寝汗の増加
睡眠時無呼吸症候群を放置すると、高血圧や糖尿病、脳梗塞などのリスクが高まることが分かっています。また、居眠り運転による交通事故のリスクも高まります。
睡眠時無呼吸症候群の診断方法
睡眠時無呼吸症候群の診断には、まず問診が行われます。その後、睡眠中の状況を把握するために自宅での簡易検査が行われることが一般的です。
手や指にセンサーを装着し、無呼吸による低酸素状態を測定する検査と、鼻に呼吸センサーを装着して気流やいびきを測定します。検査装置は手首式血圧計を少し大きくした程度の大きさで、センサーをつける以外は普段と同じように寝ていれば測定できる検査です。
より詳細な検査が必要な場合には、PSG検査(ポリソムノグラフィー検査)が行われます。これは入院して行う検査で、脳波や呼吸状態、酸素飽和度などを総合的に測定します。
睡眠時無呼吸症候群と夜間頻尿の関連メカニズム
睡眠時無呼吸症候群がなぜ夜間頻尿を引き起こすのか。そのメカニズムは主に二つあります。
1. 心臓への負担と利尿ホルモンの分泌
睡眠時無呼吸症候群で呼吸が止まると、上気道が閉塞します。すると胸腔内圧が低下し、陰圧に引っ張られるように心臓に帰ってくる血液量が増加します(静脈還流量の増大)。
この心臓負荷により、心臓の部屋の一つである右房が拡張し、心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)が産生されます。名前の通り、このホルモンには利尿作用があり、尿の産生を増加させるのです。
健康な人は覚醒時と睡眠時のANPの量に大きな差がないものの、睡眠時無呼吸症候群の患者さんは、睡眠時のANPの量が覚醒時よりも多くなることが研究で明らかになっています。
2. 自律神経系への影響
通常、睡眠中は体を休めるため、副交感神経(リラックス神経)が優位になります。副交感神経の緊張緩和により、膀胱容量は昼間の約1.5倍程度に増加するとも言われています。
しかし、睡眠時無呼吸症候群の患者さんは、無呼吸や低呼吸による低酸素状態が続くことにより、交感神経(緊張神経)が優位となります。この状態では寝ているつもりでも疲れが取れません。
交感神経が優位になると、膀胱の容量が減少するため尿が貯められずに頻尿になるのです。
研究から見る睡眠時無呼吸症候群と夜間頻尿の関係
最新の研究によると、閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)患者の男性では35.2%、女性では59.8%に夜間頻尿が認められることが分かっています。
特に注目すべきは、夜間頻尿群と非夜間頻尿群の間で見られる差です。夜間頻尿群は男女ともに年齢が高く、うつ病評価尺度、睡眠品質指数、不眠症重症度指数のスコアが高い傾向にあります。
睡眠ポリグラフ(PSG)パラメータの分析では、男性の夜間頻尿群では90%酸素飽和度低下指数(90% ODI)の高さ、N3睡眠(深い睡眠)の減少、入眠後の覚醒時間の延長など、低酸素症関連パラメータと睡眠の質パラメータが非夜間頻尿群よりも不良でした。
多変量ロジスティック解析の結果、OSAS男性患者における夜間頻尿の独立した危険因子として、年齢(オッズ比1.036)、糖尿病(オッズ比1.847)、心血管疾患(オッズ比2.658)、そして特に90% ODI(オッズ比1.020)が同定されました。
一方、女性患者では年齢(オッズ比1.030)のみが独立した危険因子として特定されました。
性差による影響の違い
興味深いことに、睡眠時無呼吸症候群による夜間頻尿への影響には性差があることが分かっています。男性では低酸素症関連パラメータが夜間頻尿と強く関連していますが、女性ではそのような関連は見られませんでした。
この理由として、女性の場合は加齢に伴う排尿機能障害と尿路疾患の影響が、睡眠時無呼吸症候群の影響を上回っている可能性が考えられます。
また、女性のOSAS患者は男性よりも低酸素関連指標が低いことも指摘されています。これは、女性の無呼吸指数が低呼吸指数よりも有意に低いことからも裏付けられています。
睡眠時無呼吸症候群の治療による夜間頻尿の改善
睡眠時無呼吸症候群の治療により、夜間頻尿が改善することが多くの研究で報告されています。主な治療法には以下のようなものがあります。
CPAP(シーパップ)治療
CPAP(Continuous Positive Airway Pressure:経鼻的持続陽圧呼吸療法)は、睡眠時無呼吸症候群の最も一般的な治療法です。寝ている間に専用のマスクを装着し、加圧した空気を鼻から送り込むことで、睡眠中の無呼吸が起こらないように機械が自動でサポートします。
CPAP治療を開始すると、夜間頻尿の回数が減少したという報告が多くあります。これは、CPAPによって上気道の閉塞が防止され、胸腔内圧の低下が起こらなくなるため、心房性ナトリウム利尿ペプチドの分泌が抑えられるからです。
また、低酸素状態が改善されることで、交感神経の過剰な活性化も抑えられ、膀胱容量の減少も防ぐことができます。
CPAP装置は、一定の基準を満たせば健康保険が適用され、機材をレンタルすることができます。自己負担額の目安は、3割負担の方で概ね毎月5,000円程度です。
その他の治療法
CPAP以外にも、睡眠時無呼吸症候群の治療法としては以下のようなものがあります。
- ・マウスピース:下顎を前方に出すことで、気道を確保するための装置です。
- ・ASV(Adaptive Servo-Ventilation):中枢性睡眠時無呼吸症候群に効果的な人工呼吸器の一種です。
- ・手術療法:扁桃腺や口蓋垂の切除など、上気道の閉塞を改善するための手術です。
- ・生活習慣の改善:体重管理、禁煙、アルコール摂取の制限などが含まれます。
これらの治療を行うことで、睡眠時無呼吸症候群が改善し、結果として夜間頻尿も軽減することが期待できます。
夜間頻尿の総合的な対策
夜間頻尿の改善には、睡眠時無呼吸症候群の治療だけでなく、総合的なアプローチが必要です。以下に、夜間頻尿を改善するための対策をご紹介します。
生活習慣の改善
夜間頻尿を改善するためには、まず生活習慣の見直しが重要です。
- ・夕方以降の水分摂取を控える:特に就寝前2〜3時間は水分摂取を最小限にしましょう。
- ・カフェインやアルコールを控える:これらには利尿作用があり、尿量を増やす原因となります。
- ・就寝前に必ずトイレに行く:膀胱を空にしてから就寝することで、夜間の排尿回数を減らせる可能性があります。
- ・適度な運動:日中の適度な運動は、夜間の良質な睡眠につながります。
医学的治療
生活習慣の改善だけでは効果が不十分な場合は、医学的治療も検討する必要があります。
- ・睡眠時無呼吸症候群の治療:前述のCPAPなどの治療を行います。
- ・薬物療法:抗コリン薬や抗利尿ホルモン製剤などが処方されることがあります。
- ・前立腺肥大症の治療:男性の場合、前立腺肥大症が原因となっていることもあるため、α遮断薬などの治療が行われることがあります。
夜間頻尿の原因は複合的であることが多いため、泌尿器科医と睡眠専門医の連携が重要です。両方の専門医による総合的な評価と治療計画が、効果的な改善につながります。
まとめ:見逃せない危険信号としての夜間頻尿
夜間頻尿は単なる不便な症状ではなく、睡眠時無呼吸症候群という重大な疾患の危険信号である可能性があります。特に、いびきがひどい、日中の眠気が強いなどの症状がある方は、睡眠時無呼吸症候群を疑う必要があります。
研究結果から、特に男性の睡眠時無呼吸症候群患者では、低酸素症の重症度(90% ODIで評価)が夜間頻尿と強く関連していることが明らかになっています。睡眠中に重度の低酸素症を呈する男性患者は、夜間頻尿についての評価を受けるべきでしょう。
逆に、原因不明の夜間頻尿に悩まされている方は、睡眠時無呼吸症候群の可能性も考慮する必要があります。夜間頻尿の治療だけでなく、睡眠時無呼吸症候群の検査と治療を並行して行うことで、より効果的な改善が期待できます。
睡眠時無呼吸症候群は放置すると、高血圧、糖尿病、脳卒中、心筋梗塞などの重大な疾患のリスクを高めます。夜間頻尿という症状を通じて、このような重大な疾患を早期に発見し、治療につなげることができれば、健康寿命の延伸にも貢献できるでしょう。
夜間頻尿でお悩みの方は、ぜひ泌尿器科や睡眠専門外来を受診してください。適切な検査と治療により、夜間頻尿の改善だけでなく、全身の健康維持にもつながります。

〈著者情報〉
泌尿器日帰り手術クリニック
uMIST東京代官山 -aging care plus-
院長 斎藤 恵介