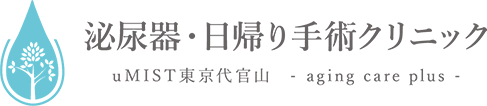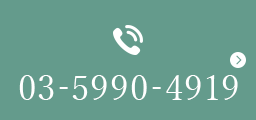夜間頻尿に悩む患者が増加している現状
夜間、排尿のために1回以上起きる症状を夜間頻尿と呼びます。健康な方でも夜間に1回起きることはありますが、臨床的に問題となるのは夜間2回以上起きる場合です。この症状は年齢とともに増加し、70歳以上になると半数以上、80歳を超えるとほとんどの方が夜間2回以上トイレに起きているという報告もあります。
私が泌尿器科医として診療していると、「年だから仕方ない」と諦めている患者さんが非常に多いことに気づきます。しかし、夜間頻尿は単なる加齢現象ではなく、様々な原因があり、適切な治療で改善できる可能性があるのです。
夜間頻尿が続くと慢性的な睡眠不足を引き起こし、昼間の眠気や疲労感が生じて日常生活に支障をきたします。さらに深刻なのは、夜中にトイレに行く際の転倒リスクです。夜間頻尿のある方は、ない方と比較して骨折による入院率がほぼ倍増するというデータもあります。
最近の研究では、夜間頻尿のある方は死亡率も2倍以上になるというデータも示されています。また、要介護となる率やうつ病になる率も高まることが分かっています。このように、夜間頻尿は単なる不便さだけでなく、健康と生活の質に深刻な影響を及ぼす症状なのです。

目次
夜間頻尿の多様な原因と睡眠障害との関連
夜間頻尿の原因は大きく分けて3つあります。
①多尿および夜間多尿(夜間に尿量が増える)
②膀胱容量の減少(前立腺肥大症や過活動膀胱など)
③睡眠障害・不眠です。
これらの原因はそれぞれ治療法が異なるため、まず原因を特定することが重要です。
私の臨床経験では、夜間頻尿の患者さんは、この3つの原因のうち2つ以上を持ち合わせていることが多いです。特に夜間多尿がある場合、薬物治療だけでは効果が限定的なケースも多く、生活習慣の改善が重要になります。
睡眠障害と夜間頻尿は密接な関連があります。睡眠の質が低下すると、夜間頻尿が起こりやすくなり、逆に夜間頻尿によって睡眠が分断されると睡眠の質がさらに低下するという悪循環に陥ります。
人は眠っている状態には、浅い睡眠状態である「レム睡眠」と深い睡眠状態の「ノンレム睡眠」という2つの睡眠状態があります。睡眠の前半に深い睡眠である「ノンレム睡眠」が集中し、睡眠の後半から起床時間に近い時間では、浅い睡眠であるレム睡眠が集中しています。
夜間頻尿によって、この深い睡眠に入る「ノンレム睡眠」が妨げられると、熟睡できなくなる原因となります。特に就寝から最初の3時間は、良質な睡眠を取れる重要な時間帯です。この時間帯に排尿で目が覚めると、睡眠の質が大きく低下してしまいます。
メラトニンと夜間頻尿の意外な関係性
メラトニンは、脳の松果体から分泌される「睡眠ホルモン」として知られています。日中は光の刺激によって分泌が抑制され、夜間になると分泌量が増加します。このメラトニンの分泌リズムが私たちの体内時計を調整し、自然な睡眠・覚醒サイクルを維持しているのです。
近年の研究では、このメラトニンが夜間頻尿と密接な関係があることが明らかになってきました。メラトニンには睡眠を促進する作用だけでなく、夜間の尿量を調節する働きもあるのです。
メラトニンが正常に分泌されると、抗利尿ホルモン(バソプレシン)の働きを助け、夜間の尿量を減少させる効果があります。つまり、メラトニンの分泌が減少すると、夜間の尿量が増加し、夜間頻尿を引き起こす可能性があるのです。
加齢とともにメラトニンの分泌量は減少します。これが高齢者に夜間頻尿が多い理由の一つと考えられています。また、ブルーライトの過剰な曝露や不規則な生活リズムもメラトニン分泌を抑制する要因となります。
私の臨床経験では、スマートフォンやタブレットなどの電子機器を就寝直前まで使用している患者さんに夜間頻尿が多い傾向があります。これらの機器から発せられるブルーライトがメラトニンの分泌を抑制し、結果として夜間頻尿を悪化させている可能性があるのです。
睡眠時無呼吸症候群と夜間頻尿の密接な関係
睡眠時無呼吸症候群(OSAS)と夜間頻尿の関連性については、近年多くの研究が行われています。OSASは睡眠中に呼吸が何度も停止する病気ですが、夜間頻尿を訴える患者さんの多くがOSASを合併しており、OSAS患者の約50%に夜間頻尿がみられるという報告があります。
私が所属する大学病院での研究でも、OSAS男性患者の35.2%、女性患者の59.8%に夜間頻尿が認められました。特に注目すべきは、OSAS患者に陽圧呼吸療法を施すと夜間頻尿の回数が減少したという報告です。これはOSASが夜間頻尿の主な原因の一つであることを示唆しています。
OSASにおける夜間頻尿の生理的メカニズムはいくつか考えられています。睡眠中の呼吸障害により胸腔内が陰圧状態になると、心臓への静脈血流量が増加します。これにより血漿および尿中の心房性ナトリウム利尿ペプチドの分泌が増加し、抗利尿ホルモンの分泌が抑制されるため、尿濃縮が阻害され、夜間多尿が生じると考えられています。
また、OSASによって引き起こされる周期的な低酸素状態が膀胱の不安定性を引き起こし、夜間頻尿につながるという説もあります。特に注目すべきは、OSASの重症度(AHI)ではなく、90%酸素飽和度低下指数(90% ODI)という低酸素関連パラメータが、男性OSAS患者の夜間頻尿の独立した危険因子であることが研究で明らかになった点です。
つまり、OSASの患者さんでは、睡眠中の低酸素状態が夜間頻尿を引き起こしている可能性が高いのです。この知見は、OSAS患者の夜間頻尿の治療アプローチを考える上で非常に重要です。
性差による夜間頻尿の特徴と対策の違い
夜間頻尿の発症メカニズムやリスク因子は男女で異なります。研究によると、50歳未満では夜間頻尿は男性よりも女性に多く見られますが、50歳以上になると男性の夜間頻尿の頻度が急激に増加します。
私たちの研究でも、OSAS患者における夜間頻尿の有病率は女性(59.8%)の方が男性(35.2%)よりも高いという結果が出ています。しかし、興味深いことに、夜間頻尿の原因となる要因は性別によって異なっていました。
男性OSAS患者では、年齢、糖尿病、心血管疾患、そして特に90%酸素飽和度低下指数(90% ODI)が夜間頻尿の独立した危険因子として同定されました。一方、女性OSAS患者では年齢のみが独立した危険因子でした。
この性差の理由としては、女性のOSAS患者は男性よりも低酸素関連指標が低いことが考えられます。女性患者の無呼吸指数は低呼吸指数よりも有意に低く、男性患者では両者に差がなかったことから、女性のOSAS患者は男性よりも低酸素症の程度が軽い可能性があります。
また、女性の場合、加齢に伴う排尿機能障害と尿路疾患がOSASの影響を上回っている可能性も考えられます。これらの性差を考慮した治療アプローチが必要です。
夜間頻尿改善のための実践的アプローチ
夜間頻尿の改善には、原因に応じた適切なアプローチが必要です。ここでは、特にメラトニンと睡眠の質に着目した実践的な対策をご紹介します。
メラトニン分泌を促進する生活習慣
メラトニンの分泌を促進するためには、以下の生活習慣が効果的です。
まず、朝の日光浴が重要です。午前中に太陽の光を浴びることで、体内時計がリセットされ、夜間のメラトニン分泌が促進されます。朝の散歩や通勤時に意識的に日光を浴びるようにしましょう。
次に、就寝前のブルーライト対策です。スマートフォンやタブレット、パソコンなどから発せられるブルーライトはメラトニンの分泌を抑制します。就寝の2時間前からはこれらの機器の使用を控えるか、ブルーライトカットメガネやフィルターを使用しましょう。
規則正しい生活リズムも重要です。毎日同じ時間に起床し、同じ時間に就寝することで、体内時計が整い、メラトニンの分泌リズムも安定します。休日も平日と同じ時間に起きるよう心がけましょう。
適度な運動も効果的です。特に夕方の軽い運動(散歩や掃除など)は、昼間に貯留した水分を血管内に戻し、汗として体外に排出する作用があります。また、適度な疲労感も得られ、入眠しやすくなります。ただし、激しい運動は就寝の3時間前までに終えるようにしましょう。
夜間多尿を減らすための水分管理
夜間多尿の改善には、水分摂取の管理が重要です。1日の適切な水分摂取量は、体重1kgあたり20〜25mlが目安です。例えば、体重60kgの方なら1.2〜1.5リットルです。このうち食事から約6割の水分が摂取されるため、飲み物としては500〜600ml程度が適量となります。
特に重要なのは、水分摂取のタイミングです。朝から昼にかけて積極的に水分を摂り、夕方以降は控えめにしましょう。就寝の2時間前からは水分摂取を最小限にすることで、夜間の尿量を減らすことができます。
また、利尿作用のある飲み物(コーヒー、緑茶、アルコールなど)は、特に夕方以降は控えるようにしましょう。これらの飲み物は尿量を増やすだけでなく、睡眠の質も低下させます。
睡眠の質を高めるための環境整備
良質な睡眠のためには、睡眠環境の整備も重要です。寝室の温度は20℃前後、湿度は40〜70%程度が理想的です。また、寝室は暗く静かな環境に保ちましょう。必要に応じてアイマスクや耳栓の使用も検討してください。
寝具も睡眠の質に大きく影響します。自分に合った硬さの寝具を選び、定期的に取り換えることで、睡眠中の体圧分散が改善し、熟睡しやすくなります。
就寝前のリラックスタイムも大切です。入浴、ストレッチ、読書など、自分なりのリラックス方法を見つけ、就寝前の習慣にしましょう。特に入浴は体温調節に効果的で、ぬるめのお湯(38〜40℃)に20分程度つかることで、その後の体温低下とともに自然な眠気が訪れます。
メラトニン受容体作動薬の可能性と限界
メラトニン受容体作動薬は、メラトニンの働きを模倣または増強する薬剤です。日本では、ラメルテオン(商品名:ロゼレム)が不眠症治療薬として承認されています。この薬剤はメラトニン受容体に選択的に作用し、自然な睡眠を促進する効果があります。
研究では、メラトニン受容体作動薬が夜間頻尿に対しても効果を示す可能性が示唆されています。メラトニン受容体作動薬は、睡眠の質を改善するだけでなく、抗利尿ホルモンの作用を補助することで夜間の尿量を減少させる効果も期待できます。
しかし、メラトニン受容体作動薬には限界もあります。まず、すべての夜間頻尿患者に効果があるわけではありません。特に、膀胱容量の減少や前立腺肥大症が主な原因の場合は、効果が限定的です。また、長期的な安全性や有効性についてはさらなる研究が必要です。
私の臨床経験では、特に睡眠障害を伴う夜間頻尿患者に対して、メラトニン受容体作動薬が効果を示すケースがあります。ただし、薬物療法だけでなく、生活習慣の改善を併用することで、より良い結果が得られることが多いです。
メラトニン受容体作動薬の使用を検討する際は、必ず医師に相談し、適切な診断と治療計画のもとで使用することが重要です。自己判断での使用は避けてください。
夜間頻尿の総合的管理アプローチ
夜間頻尿の効果的な管理には、原因に応じた総合的なアプローチが必要です。以下に、私が臨床で実践している管理方法をご紹介します。
排尿日誌の活用
夜間頻尿の原因を特定するためには、排尿日誌をつけることが非常に有効です。排尿日誌には、就寝と起床の時刻、排尿した時刻と量、飲水量などを記録します。これにより、夜間多尿なのか、膀胱容量の減少なのか、あるいはその両方なのかを判断することができます。
排尿日誌の分析では、1日の総尿量のうち夜間尿量が33.3%以上であれば夜間多尿と診断されます。また、1回排尿量が少ない(100ml以下)場合は膀胱容量の減少が疑われます。
排尿日誌は医療機関のホームページなどで入手できますが、自宅にある計量カップやペットボトルのキャップなどを利用して簡易的に記録することも可能です。2〜3日間の記録があれば、ある程度の傾向を把握することができます。
原因別の治療戦略
夜間頻尿の原因が特定できたら、それに応じた治療を行います。
夜間多尿が主な原因の場合は、前述した水分管理やメラトニン分泌を促進する生活習慣の改善が基本となります。必要に応じて、抗利尿ホルモン製剤(デスモプレシン)の使用も検討します。ただし、高齢者では低ナトリウム血症のリスクがあるため、慎重に使用する必要があります。
膀胱容量の減少が主な原因の場合は、過活動膀胱治療薬(抗コリン薬やβ3作動薬)の使用を検討します。また、男性の前立腺肥大症による排尿障害には、α1遮断薬や5α還元酵素阻害薬などの治療が効果的です。
睡眠障害が関与している場合は、睡眠衛生指導や必要に応じて睡眠薬の使用を検討します。特にOSASが疑われる場合は、睡眠時無呼吸検査を行い、陽圧呼吸療法(CPAP)などの適切な治療を行うことで、夜間頻尿の改善が期待できます。
多職種連携による包括的アプローチ
夜間頻尿の管理には、泌尿器科医だけでなく、睡眠専門医、循環器内科医、精神科医など、多職種の連携が重要です。特に、睡眠障害や循環器疾患を合併している場合は、それぞれの専門医との協力が不可欠です。
また、看護師、薬剤師、理学療法士、栄養士なども、患者さんの生活指導や服薬管理、運動療法、食事指導などの面でサポートします。このような多職種連携による包括的なアプローチが、夜間頻尿の効果的な管理につながります。
私の臨床では、患者さん一人ひとりの状況に合わせたオーダーメイドの治療計画を立て、定期的な評価と調整を行うことで、多くの患者さんの夜間頻尿が改善しています。
まとめ:夜間頻尿とメラトニンの関係から見えてくる対策
夜間頻尿は単なる加齢現象ではなく、様々な原因が複雑に絡み合った症状です。特に、メラトニンと夜間頻尿の関係は、睡眠の質と排尿のメカニズムが密接に関連していることを示しています。
メラトニンは睡眠を促進するだけでなく、抗利尿ホルモンの作用を補助することで夜間の尿量を調節する重要な役割を担っています。加齢やライフスタイルの乱れによるメラトニン分泌の減少は、夜間頻尿のリスクを高める可能性があります。
また、睡眠時無呼吸症候群(OSAS)と夜間頻尿の関連も注目すべき点です。特に男性OSAS患者では、睡眠中の低酸素状態が夜間頻尿の独立した危険因子となっています。
夜間頻尿の改善には、原因に応じた総合的なアプローチが必要です。メラトニン分泌を促進する生活習慣の改善、適切な水分管理、睡眠環境の整備、そして必要に応じた薬物療法や睡眠時無呼吸の治療などを組み合わせることで、多くの患者さんの症状を改善することができます。
夜間頻尿で悩んでいる方は、「年だから仕方ない」と諦めず、まずは医療機関を受診して適切な診断と治療を受けることをお勧めします。夜間頻尿の改善は、睡眠の質を高め、日中の活動性を向上させ、転倒リスクを減少させるなど、生活の質の向上につながります。
メラトニンと夜間頻尿の関係についての研究はまだ発展途上ですが、今後さらなる知見が得られることで、より効果的な治療法の開発が期待されます。

〈著者情報〉
泌尿器日帰り手術クリニック
uMIST東京代官山 -aging care plus-
院長 斎藤 恵介