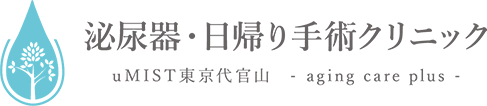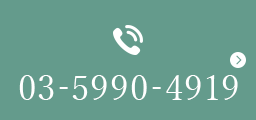睡眠回路における性差 〜 テストステロンとエストロゲン
睡眠は私たち全ての人間にとって必要不可欠な生理現象です。しかし、男性と女性では睡眠の質や量、そして睡眠障害の発生率に明確な違いがあることをご存知でしょうか?
近年の脳科学研究により、男女間の睡眠の違いには生物学的な基盤があることが明らかになってきました。本記事では、睡眠回路における性差の最新知見と、その背景にある脳内メカニズムについて詳しく解説します。
睡眠の性差を理解することは、より良い睡眠を得るための個別化された方法を見つける手がかりとなるでしょう。

睡眠における男女差の実態
睡眠は進化的に高度に保存された行動ですが、男性と女性の間には明確な違いが存在します。これらの違いは主観的な報告と客観的な測定の両方で確認されています。
興味深いことに、客観的な睡眠測定では、女性の方が男性よりも睡眠の質が良いという結果が一貫して示されています。脳波検査(PSG)による研究では、女性は男性に比べて総睡眠時間が長く、深い睡眠(徐波睡眠)の割合が高いことが報告されています。
しかし、ここで大きな矛盾が生じます。客観的には睡眠の質が良いはずの女性の方が、主観的には「眠りが浅い」「夜中に目が覚める」「寝つきが悪い」などの睡眠問題を男性よりも頻繁に報告しているのです。
さらに不眠症の有病率にも明確な性差があります。女性は男性に比べて生涯を通じて不眠症になるリスクが40%も高く、特に思春期以降にその差が顕著になります。この男女差は世界的な現象として多くの国で確認されており、女性の生理機能が不眠症において重要な考慮事項であることを示唆しています。
睡眠構造の性差
睡眠は単に「眠っている」だけの状態ではなく、複数の段階(ステージ)から構成される複雑なプロセスです。男女間では、これらの睡眠ステージの配分にも違いが見られます。
女性は男性に比べて深い睡眠(N3ステージまたは徐波睡眠)の割合が高く、睡眠強度の指標である徐波活動(SWA)も大きいことが分かっています。また、女性は年齢を問わずSWAが大きく、加齢による影響も少ないという特徴があります。
睡眠不足後の回復睡眠においても、女性は回復睡眠中のSWAが大きく、睡眠負債からより早く回復する能力を持っているようです。これは女性の睡眠が質的に優れている可能性を示唆しています。
性ホルモンと睡眠の関係
男女の睡眠の違いを生み出す主要な要因として、性ホルモンの影響が挙げられます。特に女性の場合、エストロゲンやプロゲステロンといった卵巣ステロイドの変動が睡眠に大きな影響を与えることが明らかになっています。
女性の睡眠に関する問題は、思春期、月経周期、妊娠、更年期など、卵巣ステロイドの変動期と一致する傾向があります。特に更年期移行期は睡眠障害の有病率が増加し、女性の33〜51%が睡眠の質に関する不満を報告しています。
エストロゲン補充療法が更年期の睡眠の質を改善することから、卵巣エストラジオール産生の減少が睡眠障害に関係している可能性が高いと考えられます。
月経周期と睡眠変動
健康な女性の月経周期を通して睡眠にも変化が見られます。一般的に、卵巣ステロイドのレベルが高い状態から低下し始める黄体中期に睡眠が最も妨げられる傾向があります。
中年女性を対象とした最近の研究では、不眠症の有無にかかわらず、黄体期と卵胞期の間で睡眠中の覚醒が増加し、徐波睡眠が減少することが報告されています。また、黄体期には睡眠紡錘波の数や持続時間が顕著に増加することも観察されています。
経口避妊薬などの外因性ホルモンも若い女性の睡眠に影響を与えます。経口避妊薬を服用している女性はN2睡眠とREM睡眠が増加し、徐波睡眠は減少する傾向があります。
動物モデルから見る睡眠の性差
ヒトの睡眠研究では様々な環境的・社会的要因が影響するため、睡眠の性差の生物学的基盤を理解するには動物モデルが不可欠です。げっ歯類(マウスやラット)を用いた研究からは、睡眠における性差の興味深いメカニズムが明らかになっています。
一般に、雌のげっ歯類は雄に比べて総睡眠時間が短い傾向があります。マウスでは、雌は雄に比べて総睡眠時間とノンレム睡眠が少なく、ラットでは雌はレム睡眠が有意に少ないことが報告されています。
しかし、睡眠強度の指標であるノンレム睡眠デルタパワーは、雌の方が雄よりも高いことが示されています。これはヒトでの観察結果と一致しており、雌の睡眠が質的に優れている可能性を示唆しています。
さらに驚くべきことに、性腺を摘出して血中の性ステロイドがない状態にすると、睡眠行動や睡眠構造における性差が解消されることが分かっています。これは睡眠における性差が性ステロイドに部分的に依存していることを示す重要な証拠です。
エストラジオールの睡眠調節作用
雌のげっ歯類の睡眠パターンは、卵巣ステロイドの自然な変動に非常に敏感です。エストラジオールとプロゲステロンが上昇する発情前期には、ノンレム睡眠とレム睡眠の両方が有意に減少します。
卵巣摘出ラットにエストラジオールを投与すると、暗期(活動期)の睡眠が抑制される一方、明期(休息期)の睡眠はわずかに延長することが観察されています。これはエストラジオールが睡眠と覚醒の行動を適切な時間帯に固定する役割を果たしている可能性を示唆しています。
睡眠不足からの回復においても、エストラジオールは重要な役割を果たします。エストラジオールは明期のレム睡眠回復を促進し、暗期の睡眠を抑制することで、睡眠覚醒リズムの適切な維持に貢献していると考えられます。
睡眠回路の性分化メカニズム
睡眠と覚醒を制御する脳内回路にも性差が存在することが明らかになってきました。特に注目されているのが、睡眠促進核として知られる腹外側視索前野(VLPO)です。
VLPOは睡眠に対するエストラジオールの作用を媒介していることが示されています。卵巣摘出された成体雌ラットにおいて、エストラジオールはVLPOの睡眠活性ニューロンの活性化を減少させ、睡眠を強力に促進するプロスタグランジンD2の産生を担う酵素の発現を下方制御します。
興味深いことに、雄の睡眠覚醒回路は性ステロイドの変動に対して比較的鈍感であることが分かっています。去勢してもオスのげっ歯類の睡眠や覚醒に大きな変化は見られず、テストステロンレベルの変化に対して回復力があることが示唆されています。
この性差は、発達期の性ステロイド曝露による「組織化効果」によって確立される可能性があります。脳の性分化に敏感な時期に男性化用量のテストステロンに曝露された雌ラットは、成体になってもエストラジオールとテストステロンに対して雄のような反応を示すことが確認されています。
睡眠回路の他の関連領域
睡眠における性差やステロイドによる睡眠調節には、VLPOだけでなく他の脳領域も関与しています。正中視索前核(MnPN)でエストラジオールの作用を直接阻害すると、エストラジオールによる睡眠抑制が減弱することが示されています。
また、側方視床下部にある覚醒促進ヒポクレチン/オレキシン系も、卵巣ステロイドの変動に非常に敏感であることが分かっています。エストラジオールは覚醒細胞と睡眠活性細胞の協調的な作用を介して睡眠覚醒状態に影響を与えていると考えられます。
さらに、概日リズムのマスターペースメーカーである視交叉上核(SCN)にも性ステロイド受容体が存在し、睡眠の性差に影響を与えている可能性があります。
臨床応用:性差を考慮した睡眠医療
睡眠における性差の理解は、より効果的な睡眠障害の治療法開発につながる可能性があります。実際、米国食品医薬品局(FDA)は2025年初頭、女性には一般的に処方される睡眠薬であるゾルピデム(アンビエン)の推奨用量を男性の半分にするよう勧告しました。
これは女性が男性よりもゾルピデムの代謝が遅いという発見に基づいていますが、性差や睡眠回路における卵巣ステロイドによる調節がゾルピデムに対する感受性の違いに寄与している可能性もあります。
また、健康な被験者にオランザピン(第二世代抗精神病薬)を単回経口投与した研究では、睡眠に対する薬剤の効果に明確な性差が見られました。女性では徐波睡眠が増加したのに対し、男性では徐波睡眠が減少したのです。
これらの知見は、睡眠を調節するメカニズムにおける性差の存在を裏付けるものであり、性別に応じた個別化治療の重要性を示しています。
女性特有の睡眠障害への対応
女性の睡眠障害、特に更年期に関連する睡眠問題に対しては、ホルモン療法が効果的であることが示されています。エストロゲン補充療法は睡眠の質を改善することが報告されていますが、これが睡眠メカニズムへの直接作用なのか、ホットフラッシュなどの血管運動症状の減少による間接的な効果なのかは、まだ完全には解明されていません。
また、女性の睡眠障害はうつ病のリスク増加とも強く関連しています。不眠症の発症は、うつ病のリスクが2倍になることと関連しており、卵巣ステロイド環境の変動が睡眠障害とうつ病の両方に関与している可能性があります。
女性における睡眠の卵巣ステロイド調節の根底にあるメカニズムをより深く理解することで、女性におけるうつ病の治療のための新たな治療法を発見できる可能性があります。
参考文献:睡眠における男女差:生物学的性別と性ステロイドの影響
まとめ:睡眠の性差研究の今後
睡眠における性差と、その違いを支配するメカニズムが性ホルモンに大きく依存していることを示す証拠が蓄積されています。女性の睡眠は卵巣ステロイド環境の変化に対して特に敏感であり、これが女性における睡眠障害の高い有病率に関連している可能性があります。
一方で、睡眠における性差の正確なメカニズムについては、依然として大きな知識のギャップが残されています。特に、女性の睡眠に影響を与える卵巣ステロイドの正確な作用機序や、睡眠回路における性差の発達過程については、さらなる研究が必要です。
神経内分泌系と睡眠回路系の相互作用が女性の睡眠障害リスクにどのように影響するかを理解し、女性の生理機能を考慮した適切な治療法を開発するためには、睡眠における性差と、エストロゲンによる睡眠調節という基本メカニズムの解明に向けた研究が不可欠です。
睡眠における性差とその根底にあるメカニズムを解明することは、性別に応じた個別化治療の開発につながる重要な課題であり、今後の睡眠医学の発展において中心的なテーマとなるでしょう。

〈著者情報〉
泌尿器日帰り手術クリニック
uMIST東京代官山 -aging care plus-
院長 斎藤 恵介