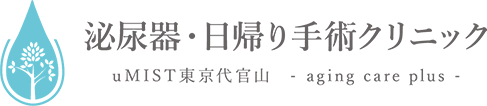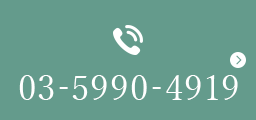排尿障害とは?日常生活に影響を及ぼす尿トラブル
「トイレに行きたい」という感覚は、私たちが当たり前のように感じている生理現象です。しかし、この感覚がうまく機能しなくなると、日常生活に大きな支障をきたします。排尿障害とは、膀胱に尿をためる機能や尿を体外に排出する機能に異常をきたした状態を指します。
排尿障害は大きく分けて「蓄尿障害」と「排出障害」の2つに分類されます。蓄尿障害は膀胱に尿をためておくことができなくなる障害で、排出障害は尿を出しにくくなる障害です。これらの症状は加齢とともに増加する傾向がありますが、単なる加齢現象ではなく、様々な疾患や生活習慣が関わっていることも少なくありません。
英国の作家ヘンリー・ミラーは「満杯になった膀胱を解放することは、人間にとって大きな喜びの一つである」と述べました。この何気ない喜びが損なわれることで、生活の質が著しく低下してしまうのです。
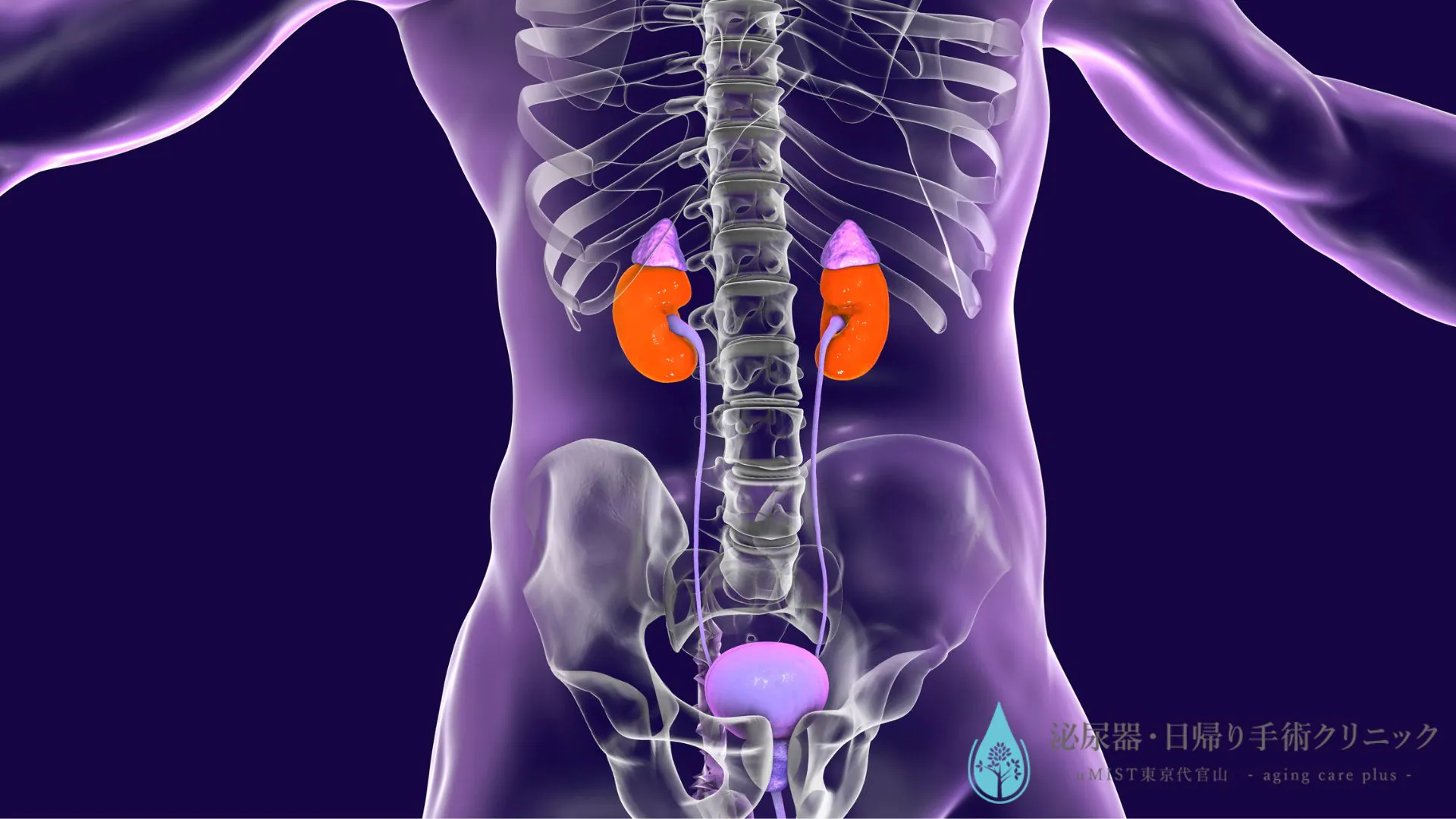
排尿障害の主な症状と分類
排尿障害の症状は実に多様で、患者さんによって訴える内容が大きく異なります。症状を正確に把握することが、適切な診断と治療につながります。
蓄尿障害の症状
蓄尿障害では、膀胱に十分に尿を貯められない状態となり、以下のような症状が現れます。
- 昼間頻尿:日中起きている間に8回以上排尿する状態
- 夜間頻尿:夜間睡眠中に1回以上排尿のために起床する状態
- 尿意切迫感:突然起きる抑えきれない尿意で、トイレに慌てて駆け込む状態
- 尿失禁:自分の意思とは関係なく尿が漏れてしまう状態
尿失禁にはさらに細かく分類があり、咳やくしゃみなどで尿が漏れる「腹圧性尿失禁」、急な尿意とともに尿が漏れる「切迫性尿失禁」、両方の特徴を持つ「混合性尿失禁」などがあります。
排出障害の症状
排出障害では、尿の排泄がうまくいかず、以下のような症状が現れます。
- 尿勢低下:尿の勢いが弱くなる
- 尿線分割・尿線散乱:尿が1本でなく2本に分かれたり、飛び散ったりする
- 尿線途絶:排尿の途中で尿線が途切れる
- 排尿遷延:尿が出始めるまでに時間がかかる
- 腹圧排尿:排尿時にお腹に力を入れ、息んで排尿する
また、排尿後に「残尿感」(排尿後もまだ尿が残った感じがする)や「排尿後尿滴下」(排尿後に下着をつけてから尿が少し漏れてくる)といった症状も見られます。
排尿障害の原因と発症メカニズム
排尿障害の原因は多岐にわたります。年齢や性別によっても原因疾患の頻度が異なりますが、最近の研究では、排尿の感覚メカニズムに関する新たな発見がありました。
男女による原因と症状の違い
男性と女性では排尿に関わる体の構造が異なるため、症状の出方や原因にも特徴があります。
男性の尿道は約20センチと長く、L字カーブを描いています。さらに前立腺という臓器に囲まれており、加齢とともに前立腺が肥大しやすい傾向にあります。そのため、男性は特に「尿を出す機能」にトラブルが発生しやすい構造になっています。男性の排尿障害の原因疾患として最も多いのが前立腺肥大症です。
一方、女性の尿道は約3~4センチと短く、カーブもありません。女性の膀胱や尿道は骨盤底筋で支えているだけなので、加齢や出産などでこの骨盤底筋群がゆるむことで「尿をためる機能」にトラブルが発生しやすくなります。腹圧性尿失禁は特に女性に多い尿トラブルです。
PIEZO2研究からわかった排尿メカニズム
最近の研究で、排尿の感覚メカニズムに重要な役割を果たしているタンパク質が発見されました。それが「PIEZO2(ピエゾ2)」と呼ばれる機械感受性イオンチャネルです。
PIEZO2は、組織への機械的な圧力や伸展・収縮の刺激が与えられたとき、細胞膜のイオンチャネルを開き、刺激を脳に伝えるセンサーの役目をしています。このタンパク質は全身のさまざまな臓器や組織に発現しており、肺の伸びを感知して呼吸を調整したり、血管内で血圧を感知したり、皮膚の触覚を媒介する役割も担っています。
研究によると、PIEZO2は膀胱尿路上皮細胞と感覚神経の両方で発現しており、低閾値の膀胱伸展感知および尿道排尿反射に必要であることが明らかになりました。つまり、膀胱が尿で満たされて伸びる感覚や、排尿時の尿の流れを感知するのに重要な役割を果たしているのです。
参考文献: 記事を読む
PIEZO2欠損がもたらす排尿障害
PIEZO2の機能が失われると、排尿にどのような影響が出るのでしょうか? 研究チームはPIEZO2欠損を持つヒト被験者とマウスを対象に調査を行いました。
PIEZO2欠損を持つヒト被験者(12名、5~43歳)の調査では、全患者で排尿頻度が減少しており、多くが排尿の必要性を感じずに過ごせると報告していました。そのため、患者たちは時間ベースの排尿スケジュールを守っていました。
私が臨床で経験した症例を一つ紹介しましょう。32歳の女性患者さんは、膀胱が満タンであるという感覚に乏しく、失禁を避けるために3時間おきに排尿するようにしていました。彼女は「おしっこしたい」という感覚がほとんどなく、排尿時に膀胱を完全に空にすることができませんでした。
このような症状は一見すると便利に思えるかもしれませんが、実際には多くの問題を引き起こします。突然の切迫性尿失禁や腹圧性尿失禁などの症状も報告されており、PIEZO2がヒトの排尿において重要な機能的役割を果たしていることが示唆されています。
マウス実験から判明した詳細なメカニズム
マウスを用いた研究では、Piezo2が膀胱感覚ニューロンの約81.5%と、膀胱内側を覆うアンブレラ細胞の74%で発現していることが確認されました。カルシウムイメージングを用いた実験では、感覚ニューロンにおける膀胱伸展反応がPiezo2依存性であることが示されました。
特に興味深いのは、低圧刺激に反応する細胞はPiezo2ノックアウトマウス(Piezo2遺伝子を欠損させたマウス)のDRG(後根神経節)では完全に消失していたことです。これは、PIEZO2が特に膀胱が少し膨らんだ程度の軽い伸展を感知するのに重要であることを示しています。
Piezo2ノックアウトマウスでは排尿反射に異常が見られ、排尿のタイミングが不規則で、膀胱収縮の間隔が長くなり、排尿に至る膀胱収縮を開始するためにより多くの量を必要としました。また、ノックアウトマウスでは排尿中の膀胱圧が高く、尿道反射が減弱していました。
長期的には、これらの排尿機能障害が膀胱壁の肥厚などの組織リモデリングを引き起こしていました。これは、慢性的な排尿障害が膀胱の構造自体を変化させることを示しています。
参考文献: 記事を読む
PIEZO2研究の臨床応用と今後の展望
PIEZO2の研究は、排尿障害の理解と治療に新たな可能性を開きました。この発見は、どのように臨床応用されるのでしょうか?
PIEZO2は膀胱尿路上皮細胞と感覚神経の両方においてセンサーとして機能することが明らかになりました。研究チームは、尿路上皮細胞特異的Piezo2ノックアウトマウスと感覚ニューロン特異的Piezo2ノックアウトマウスの両方で類似の表現型が見られることを発見しました。
これは、アンブレラ細胞と感覚神経細胞においてPIEZO2を利用して膀胱の感受性を設定し、排尿反射を促進する、2つの部分からなるシグナル伝達機構が存在することを示唆しています。
この発見は、過活動膀胱や神経因性膀胱などの排尿障害の新たな治療法開発につながる可能性があります。PIEZO2の機能を調整する薬剤が開発されれば、排尿障害の症状を改善できるかもしれません。
他のメカノセンサーとの関係
PIEZO2が欠損していても尿路麻痺や死に至ることはなく、PIEZO2を欠損したヒトでも排尿は可能です。これは、PIEZO2以外の機械伝達タンパク質が尿路上皮とLUT感覚ニューロンに存在することを示唆しています。
例えば、機械伝達イオンチャネルであるTMEM63bとPIEZO1は尿路上皮に広く発現しており、PIEZO1はin vitroにおいて尿路上皮の伸展反応を部分的に媒介することが報告されています。
このように、排尿の感覚メカニズムには複数のタンパク質が関与しており、それらが相互に補完し合っている可能性があります。今後の研究では、これらのタンパク質がどのように連携して排尿機能を制御しているのかが解明されることが期待されます。
参考文献: 記事を読む
まとめ:PIEZO2研究が排尿障害治療にもたらす可能性
排尿障害は、単なる加齢現象ではなく、様々な疾患や生理学的メカニズムが関わる複雑な病態です。PIEZO2という機械感受性イオンチャネルの発見により、排尿の感覚メカニズムに関する理解が大きく進展しました。
PIEZO2は膀胱尿路上皮細胞と感覚神経の両方で発現しており、低閾値の膀胱伸展感知および尿道排尿反射に必要であることが明らかになりました。PIEZO2欠損を持つヒト被験者は排尿頻度の減少や膀胱充満感覚の欠損などの膀胱制御障害を示し、マウス実験からもPIEZO2が排尿機能において重要な役割を果たしていることが確認されました。
この研究は、尿路上皮細胞と感覚神経が排尿を制御するためにどのように相互作用するかを解明するための基盤を提供しています。今後、PIEZO2を標的とした新たな治療法の開発が進むことで、過活動膀胱や神経因性膀胱などの排尿障害に苦しむ患者さんの生活の質が向上することが期待されます。
排尿障害でお悩みの方は、症状を我慢せず、専門医に相談することをお勧めします。適切な診断と治療により、多くの排尿障害は改善が可能です。

〈著者情報〉
泌尿器日帰り手術クリニック
uMIST東京代官山 -aging care plus-
院長 斎藤 恵介