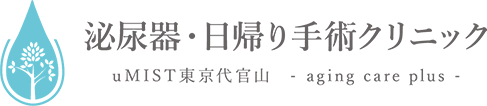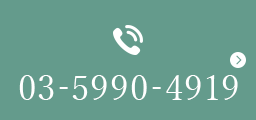排尿障害が生活の質に与える影響と新たな知見
排尿は私たちの日常生活における基本的な生理現象です。しかし、この当たり前の機能に障害が生じると、生活の質(QOL)は著しく低下します。排尿障害は単なる不快感にとどまらず、社会生活や心理面にも大きな影響を及ぼす問題なのです。
私は泌尿器科医として30年以上にわたり多くの排尿障害患者を診てきました。近年、排尿メカニズムに関する研究は飛躍的に進み、特に機械感受性イオンチャネルPIEZO2の発見は、排尿障害の理解と治療に新たな展望をもたらしています。
この記事では、排尿障害が生活の質に与える影響と最新の研究知見について解説します。

排尿障害の種類と生活への影響
排尿障害は大きく分けて「蓄尿障害」と「排出障害」に分類されます。蓄尿障害には頻尿や尿失禁などが含まれ、排出障害には排尿困難や尿閉などが含まれます。
頻尿は1日に8回以上トイレに行く状態を指します。特に夜間頻尿は睡眠の質を低下させ、日中の活動性にも影響を及ぼします。「一晩に何度もトイレに起きなければならない」という状況は、患者さんの生活リズムを根本から変えてしまうのです。
尿失禁は「自分の意思に反して尿が漏れる状態」です。腹圧性尿失禁はくしゃみや咳などで腹圧が上がった際に尿が漏れるタイプで、切迫性尿失禁は急に強い尿意を感じて我慢できずに漏れるタイプです。
こうした症状は、外出先でのトイレの心配や衣服の汚れへの不安から、社会活動の制限につながることが少なくありません。私の診察室では「旅行に行けなくなった」「友人との食事会を避けるようになった」という訴えをよく耳にします。
排尿障害は身体的な問題だけでなく、心理的な負担も大きいものです。「いつ漏れるか」という不安や「人前で恥ずかしい思いをするのではないか」という恐怖は、自己肯定感の低下やうつ状態を引き起こすこともあります。
PIEZO2の発見と排尿メカニズムの新知見
排尿のメカニズムは複雑で、長年その詳細は完全には解明されていませんでした。しかし近年、機械感受性イオンチャネルPIEZO2の発見により、膀胱の充満感覚と排尿反射の仕組みに新たな光が当てられています。
PIEZO2は2010年に発見され、その重要性から発見者のアーデム・パタプティアン博士は2021年にノーベル医学生理学賞を受賞しました。このタンパク質は組織の伸展や圧力を感知するセンサーとして機能しています。
最新の研究では、PIEZO2が膀胱尿路上皮細胞と感覚神経の両方に発現しており、膀胱の伸展感知および排尿反射に必要であることが明らかになりました。マウスを用いた研究では、膀胱感覚ニューロンの約81.5%と、膀胱内側を覆うアンブレラ細胞の74%でPIEZO2が発現していることが確認されています。
PIEZO2欠損による排尿障害
興味深いことに、PIEZO2遺伝子に変異を持つヒト被験者の調査では、全患者で排尿頻度が減少しており、多くが排尿の必要性を感じずに過ごせると報告していました。そのため、これらの患者は時間ベースの排尿スケジュールを守る必要がありました。
また、PIEZO2欠損マウスでは排尿反射に異常が見られ、排尿のタイミングが不規則で、膀胱収縮の間隔が長くなり、排尿に至る膀胱収縮を開始するためにより多くの量を必要としました。さらに、これらのマウスでは排尿中の膀胱圧が高く、尿道反射が減弱していました。
長期的には、これらの排尿機能障害が膀胱壁の肥厚などの組織リモデリングを引き起こしていたのです。
この発見は、尿路上皮細胞と感覚神経が排尿を制御するためにどのように相互作用するかを解明するための基盤を提供しています。
排尿障害が健康寿命に与える影響
排尿障害は単に不快な症状というだけでなく、健康寿命にも大きな影響を与えることが近年の研究で明らかになっています。特に高齢者において、排尿障害は転倒リスクの増加や活動性の低下につながることが問題視されています。
夜間頻尿による睡眠障害は、日中の認知機能低下や疲労感を引き起こします。十分な睡眠が取れないことで、高齢者の認知症リスクが高まるという報告もあります。
不適切な対処法がもたらす二次的問題
排尿障害に対する不適切な対処法も問題です。例えば、頻尿を避けるために水分摂取を極端に制限すると、脱水や便秘、さらには尿路感染症のリスクが高まります。
また、不必要な尿道カテーテルの留置は、尿路感染症や尿道損傷、尿道狭窄などの合併症を引き起こす可能性があります。日本は「尿道カテーテルジャングル」と呼ばれるほど不必要なカテーテル留置が多いことが問題視されています。
私の臨床経験からも、適切な排尿ケアは不必要な尿道カテーテルを抜くことから始まると言えます。急性期には必要であっても、体の状態が回復すれば抜去できる可能性が高いのです。
排尿障害を放置することで、膀胱機能がさらに低下し、最終的には「代償不全」と呼ばれる状態に陥ることもあります。これは不完全な排尿、膀胱尿管逆流、尿路感染症頻度の増加といった後遺症を伴う、弛緩した非効率的な膀胱によって特徴づけられます。
排尿障害の最新治療アプローチ
排尿障害の治療は、原因となる疾患や症状の種類によって異なります。ここでは、最新の治療アプローチについて解説します。
薬物療法の進歩
過活動膀胱に対しては、抗コリン薬やβ3アドレナリン受容体作動薬が有効です。特に近年では、β3アドレナリン受容体作動薬が副作用の少ない選択肢として注目されています。
前立腺肥大症による排尿障害に対しては、α1ブロッカーやPDE5阻害薬が第一選択薬として推奨されています。前立腺腫大が30mL以上の場合は5α還元酵素阻害薬の併用が、過活動膀胱症状が明らかな場合は抗コリン薬またはβ3作動薬の併用が考慮されます。
興味深いことに、BPH(前立腺肥大症)患者の約50~75%で、OAB(過活動膀胱)を合併するといわれており、蓄尿症状は生活の質に大きく影響することから、実臨床においては、OABを合併したBPH症例に対して治療で難渋することが多いのが現状です。
非薬物療法の重要性
薬物療法だけでなく、生活習慣の改善も重要です。適切な水分摂取、カフェインや刺激物の制限、骨盤底筋体操などが効果的です。特に女性の腹圧性尿失禁に対しては、骨盤底筋体操が第一選択の治療となります。
手術療法も進化しています。前立腺肥大症に対する経尿道的前立腺レーザー核出術や、女性の腹圧性尿失禁に対する中部尿道スリング手術などの低侵襲手術が普及しています。また、前立腺がん手術後の尿失禁に対する人工尿道括約筋植込術も有効な選択肢です。
最近では、神経調節療法や膀胱内ボツリヌス毒素注入療法など、難治性の過活動膀胱に対する新たな治療法も開発されています。
PIEZO2研究がもたらす将来の治療展望
PIEZO2の発見と排尿における役割の解明は、排尿障害治療に新たな可能性をもたらしています。この機械感受性イオンチャネルをターゲットとした治療法の開発が進めば、従来の治療では効果が不十分だった患者さんにも新たな選択肢が生まれるでしょう。
PIEZO2は膀胱尿路上皮細胞と感覚神経の両方で機能していることから、両方の細胞タイプをターゲットとした治療法の開発が期待されます。特に、アンブレラ細胞と感覚神経細胞においてPIEZO2を利用して膀胱の感受性を設定し、排尿反射を促進する2つの部分からなるシグナル伝達機構の解明は、より精密な治療法開発につながる可能性があります。
また、PIEZO2以外の機械伝達タンパク質(TMEM63bやPIEZO1など)も尿路上皮に広く発現していることが分かっており、これらをターゲットとした治療法の開発も進んでいます。
排尿障害は決して「年のせい」で諦めるべきものではありません。
適切な診断と治療により、多くの患者さんのQOLを改善することが可能です。症状でお悩みの方は、ぜひ専門医にご相談ください。
合わせて読みたい: 排尿障害の症状と原因|PIEZO2研究からわかること
まとめ
排尿障害は生活の質に大きな影響を与える重要な健康問題です。PIEZO2の発見により、排尿メカニズムの理解は飛躍的に進み、新たな治療法開発への道が開かれています。
排尿障害で悩む方は少なくありませんが、現在でも様々な治療選択肢があります。症状を我慢せず、専門医に相談することが、生活の質を向上させる第一歩となるでしょう。
私たち医療者も、最新の研究知見を臨床に活かし、患者さん一人ひとりに最適な治療を提供できるよう努めていきたいと思います。

〈著者情報〉
泌尿器日帰り手術クリニック
uMIST東京代官山 -aging care plus-
院長 斎藤 恵介